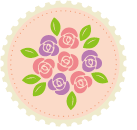
本日は、鶴川北教会創立44周年の記念礼拝を守る。今年は世界規模のウイルス禍によって、イースター、ペンテコステという教会にとって最も大切な時に、一同に会しての礼拝を守ることができなかった。「ソーシャル・ディスタンス」は教会の礼拝にまで影響を及ぼし、海外の教会では、神父が祝福の聖水を皆に振りかけるに、水鉄砲を用いる等、「子どもの遊び」にしか見えない様子も伝えられた。しかしそれはそれでまた、天国のような風情である。
今日、兎にも角にも、この教会で、皆さん方と共に礼拝を守ることのできる恵みを思う。そして未だ「病気」におののく不安の中にあっても、「創立記念礼拝」において「洗礼式・信仰告白式」の時が与えられることに、神のみこころの深さを思う。人間の世界がどのような状態であっても、怖れ、おののき、悩みの中でも、神は、私たちにみ言葉をもって、今、語り続けて下さっているのである。そのみ言葉をしっかりと心に刻み付けたいと思う。
1979年5月末に、完成したこの教会堂で、初めての礼拝が守られた。その年の伝道集会の説教で、八木重吉の詩の一篇が、引用されている。「はじめにひかりがありました/ひかりは/哀しかったのです」。「私たち人間が愛や信頼を語っていても空しいとしかいいようのな状況を彼は『ひかりは哀しかったのです』というのです。しかし『それでも/人は/愛せずには/憎まずには/怒らずには/どうしても/おれないのです』と彼はいい、『いつの世に、愛のみの世が来ますか』と悲しんでいます」。当時のこの教会の牧師、牧野信次氏の言葉である。
会堂が完成し、そこで礼拝が守られ、人々が集められ、教会が形作られて来た。教会が立つこの世界は、「人間が愛や信頼を語っても、空しいというしかない」場所なのである。この数カ月の間、私たちは「新しい生活様式」なるものに従って生活せざるを得ないでいる。「外には戦い、内には怖れ」とパウロが看破した如く、内に籠り、ひたすら見えない敵を恐れ、息をひそめて暮らして来たといっても過言ではない。ではそこで何が起きて来たのか。今まで目を反らし、あるいは伏せられ、隠されていたものが、表に現れてきたのである。例えば、忙しく生活に追われる日々の労苦(ルーティン)が、実はそれほど必要ではなかった、あるいは自分が必死にならなければ立ち行かない、という切実な思いも、単に思い込みであった。即ち「人間が愛や信頼を語っても、空しいというしかない」という現実を知らされた。そして、そこに教会は立てられているのである。
そしてその「はじめに」何があったのか、人間の信念、展望や計画のずっと前に、先んじて何があったか。「ひかりがあった」とこの町田出身の、まだ若くして家族を残してこの世を去った詩人の言葉と共に、創立間もないこの時、牧師は語るのである。「ひかりがあった」。「ひかりは哀しかった」。
今日の聖書に、18節「あなたがたは手で触れることができるものや、燃える火、黒雲、暗闇、暴風、ラッパの音、更に、聞いた人々がこれ以上語ってもらいたくないと願ったような言葉の声に、近づいたのではありません」と語られる。世の中には、人間の傷ついた心に、さらに塩をもみ込むような、荒々しい言葉に満ちている。「愛と信頼」が語られても、それを軽蔑し、踏みにじろうとする空しい言説に満ちている。それを一国の指導者が率先して行うのである。他に負けない強さと強靭さだけが褒めたたえられるべきもので、優越性だけが人間の価値であるかのように、ふるまうのである。「これ以上語ってもらいたくないと願ったような言葉の声に、近づいたのではありません」、このみ言葉は、私たちの心そのままである。かの出エジプトを率いた猛者モーセでさえも「わたしはおびえ、震えている」と本音を吐いた、という。
皆さんはどうか。今のこの世界に、自分が生きているこの世界に「わたしはおびえ、震えている」と感じてはおられないか。新聞にこんな記事が掲載されていた。「おい、マスクはどうした」。マスクの品切れが続いていたころ、商店街を歩いていると突然、がなり声が聞こえた。振り向くと、初老の男性が道端で、幼い女の子をとがめている。その口元にマスクはない。のどかな昼下がりに、不穏な空気が流れた。正体不明の新型コロナは、社会の不安と不信を増幅させた。感染への恐怖心がとげとげしい言葉となって飛び交い、休業しない店や外出する人を過剰に非難する動きがある。見えないウイルスが人の心までむしばんでいるようだ。すごむ男性に私まで身構えていると、女の子は「忘れちゃった」とにっこり。緊迫はとたんに緩み、男性も「うちに100枚ある。やろうか」と力の抜けた様子。子どもの笑顔には、コロナですさんだ心を包み込む不思議な力がある。(山下真)西日本新聞記者コラム6月7日付
だから「ひかりは哀しかったのです」。詩人は、「おびえ、震えている」世界を、哀しみ、いとうしい思いで慈しむ、「ひかり」があることを歌っている。ひかりはすべてのものを映し出す働きをする。隠しておきたい人間の罪や、過ちや、愚かさもすべて表に引きずり出すであろう。しかし「ひかり」は、無慈悲に人間の罪を一刀両断に捌くのではない。深く哀しむのである。「新しい契約の仲介者イエス、その注がれた血」、つまり「ひかり」はこの世界を哀しみ、十字架を負い、その上で血を流される、哀しみのゆえに、己を引き裂く、というのである。わたしたちはこの哀しみのひかりに、近づくのである。
記念誌『十年の歩み』の中で、ある教会員の方が、ひとつの詩を綴っておられる。「主よ~献堂の日によせて~」と題されている。「主よ/お疲れになられたのではないでしょうか。この十年余/あなたは/私たちとともに/否/私たちを引きずるようにして/この鶴川の地を/あちこちと お歩きくださいました。雑貨店(スーパー)の二階にも/学習塾の教室にも/あなたは/気軽に お立ちになりました。あなたが/立ち現れるところ/どこでも/立ちどころに/教会となり 礼拝の場所となりました」。
まるで出エジプトの後の、イスラエルの人々の荒れ野の彷徨を思い起こさせるような風情である。主はいつでも、どこでも、世界のあたりまえの場所で、私たちの日常に、み言葉を語り続けて下さった、み言葉をもって導いてくださった、というのである。だから「あなたがたは語っている方を拒むことがないように気を付けなさい」。