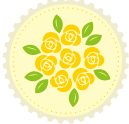
「暑さ寒さも彼岸まで」と言われる。日々に秋めいてくる季節を迎えた。今年の夏も暑かった、何度、口にしたことだろう。「甲子園」というと夏の季語になっているほど、この国の風物詩である。兵庫県西宮の甲子園球場で開催される高校野球大会である。しかし「甲子園」の名をかぶせているのは、野球ばかりでない。8月18日に盛岡市で、「短歌甲子園」が開催された。「短歌」を詠んで、2つのチームが競い合う。
団体戦決勝の大将戦では、沖縄の高校生らが、作品を披露した。島袋さんの歌「灰色の箱が生み出す爆音は 今か 咲く花ただ揺らすのみ」。「灰色の箱」をフェンスで囲われた米軍基地に見立て「咲く花」に地域住民や生活する自身を重ねた。國吉さんの作品「碧海(へきかい)に コンクリートを流し込み 儒艮(じゅごん)の墓を建てる辺野古に」。
この学校のクラブ顧問が、こういう感想を寄せている。本校文芸部が「短歌甲子園2019」で全国準優勝を果たした。短歌が門外漢の私にできるアドバイスは一つだけ。「歌は『私』を離れては生まれない。『暮らし』に寄り添う歌を作ってごらん」。彼女たちは言いつけを守った。身の回りの知覚、体験を繊細な感性によって美しい調べに結晶させる。歌が一つ詠まれる度に会場が揺れた。厳かな沈黙が人々を包む。祈りにも似た歌は、審査員はもちろん観客の心を捉えたと感じた。胸が熱くなった。感動した。
しかし、居心地の悪さがなぜか拭えない。それが「若者への申し訳なさ」だと気づいたのは帰りの飛行機の中だった。本土の若者が作る歌には、我が街の不安、憤り、悲しみがない。あるのはただ“わがまま”で“ぜいたく”な青春の謳歌(おうか)だった。切ない恋心、青春の葛藤、家族や友への感謝…。思わず考え込む。なぜ沖縄の若者だけが今も憤り、悲しみを伝える義務を負うのか。いつまで基地、戦争に拘ればいいのだろうか。
歌というと、「真、善、美、愛」というイメージが強いが、そこにも作家自身の抱える現実、多くは深刻な現実の有様が、そのまま裏側に投影されている、と言えるだろう。神は世界を「無」から創造したといわれるが、人間は、まったくの空、空っぽでは、虚構の世界でさえも作り出すことはできない、ということか。そこにはどうしても、自分の抱える具体的な問題や課題が、顔を覗かせるのである。
今日はガラテヤ書から話をする。その末尾の部分である。6章11節からお終いまで「結びの言葉」と題されている。その11節に、興味深い文言が記されている。「自分の手であなたがたに書いています」。学者たちはこう解説する。「ここまでパウロは、当時の慣習にならって、書記に口述筆記させ、手紙を記して来た。しかしここにきて、彼は、自らペンを取って、自筆で手紙を認めたのである。もしかしたら、ここから手紙の一番最後まで、彼自身が直接、文章を綴った可能性がある」。普通、差出人はサイン代わりに一筆啓上、直筆で短く挨拶するというのが当時の習慣であった。それを破ってまで、長々と自筆で手紙の最後の文言を記したというのは、やはりガラテヤ教会への思い入れの強さ、深さ、そして抑えきれない心情が、最後に噴き出たというところであろう。
パウロは学識のある知識人だったが、字を書く専門家ではない。その道のプロは、時代の慣例に従った書式に則って、文書を認めた。パピルス紙一枚に、既定の文字数、行数を守って、きれいに筆記をする。現在でも、聖書の写本の断片らしい紙切れが、発見されることがたまにある。たとえどんなに小さな断片でも、そしてそれが虫食いでぼろぼろでも、聖書のどの個所なのか、見当がつけられるのも、そういう事情がある。
しかしパウロはプロの書記ではない。「今、こんなに大きな字で」とは、いろいろな想像が広がって、楽しい。きっちりした整った文字ではない。「仲よきことは美しき哉」とか「人間だもの」とかいう風な、あんな「へたうま」の文字だったのではあるまいか。あるいは「こんなに大きな字で」というのは、彼が、目が悪かったからではないか。彼は病気に終生悩まされたが、その病気とは実は「眼病」だったのではないか。いろいろ彼の抱える現実が、想像されるのである。
そして、どうして自筆で最後の言葉を記したのか、その動機も推し量ることができるのである。直筆で書く、今も終活している学生の質問に、「履歴書は自筆でなくてはいけませんか」というのがある。コンピュータで文字を記す時代である。でも「自筆」の意味は何であろう。「自分の本気度の証」あるいは「自己証明のしるし」であろう。誰でもない、この私が記した、私の本気のこころ、が相手に伝わるという訳である。パウロも同じではないのか。なかなか、自分の真実な思いを分かってくれない、ガラテヤ教会の人々に、つい「ああ、この鈍い馬鹿者が」と口走ってしまったパウロである。他人行儀でなく真心を通じるために、パウロは最後に、自分で文章を記すのである。
パウロが語りたい、一番のまことは何か、それ程長くもない文言の中に、それが明瞭に表れている。何度も何度も繰り返される言葉がある、それが「十字架」である。この単語は、元々「棒ぐい」という意味の言葉である。「十文字に組み合わされた木材」という丁寧な意味の言葉ではない。「棒ぐい」いささか乱暴な意味合いの用語である。つまり、当時の人々は「十字架」を軽蔑の、唾棄すべき、目を背けたくなるようなものとして考えていたことが、単語そのものから知れるのである。
パウロはその皆が目を背ける十字架を、自分の考えや議論の真正面に据えて語るのである。世俗の人ばかりでない、実に教会に属するキリスト者でさえも、目を反らそうとしていたのである。その中心が14節「引用」。パウロにとって「十字架」こそが、主イエス・キリストの真実、中心であった。自分には十字架以外にない。しかし、「十字架」こそ、迫害の一番の根、原因だったのである。
当時のローマ帝国では、ハドリアヌスの時代を除けば、ユダヤ人の立場はそう悪いものではなかった。むしろユダヤ教はローマの公の祭祀以外に公認された唯一の宗教だった。ローマ人の間では、偶像崇拝をやめ、安息日や一定の食事の禁止(恐らく豚肉食のこと)を守る、いわば「ゆるいユダヤ教」が流行した時期があり、上流社会から宮廷にまで信奉者がいた。合理的なローマ人の気質、多神教の良く言えば寛容な、悪く言えば節操を欠いた雰囲気の中で、気まぐれな興味本位だったかも知れないが、一定の地位を保っていた。キリスト教会も、「ちょっと新しめのユダヤ教です、ユダヤ教の親戚です」と名乗っていたなら、おそらく迫害は起きなかっただろう。12節「引用」の通りである。しかしパウロは主イエスの十字架をはっきりと語り、信仰の真正面に据えたのである。
十字架を口にするということはどういうことか、それは誰が、なぜ神の子を十字架に付けたかを語ることになる。主イエスの十字架は、ローマとユダヤの、神に対する深い罪を告発するものとなる。「誇り」とパウロは言うが、人は見栄えの良い、誰かに自慢できる、華々しいものに引かれる。大勢の者が集まり、列を作って並んでいたら、そこには良いもの、素晴らしいものがあるように思い、自分もまたそこに行こうとする。信仰の変質は、サタンの顔をもってではなく、人々が受け入れやすいもっともらしい言い分をもってやって来る。
人間の「誇り」とはつまるところ「自慢」である。人は自分の優れているところ、大きなところ、美しいところを外に表そうとする。しかし主イエスは、人間となり自分を小さくして、十字架で血を流し、まったく無力な姿で、息を引き取られた。神の誇りは、栄光の内に輝くばかりの、麗しい姿で大衆の前に現れることではなく、みじめに打ちひしがれて、絶望の中に自分のありのままを示すことであった。それによって、私たち人間の人生の、とことんまで、極みまで、共に生きるためである。そこまで私たち人間の下に、歩み寄ってくださった、ここに主イエスの十字架の誇りがある。
この十字架によって、私たちの人生は、世界のすべては、計られ裁かれるのである。大きさや、うるわしさ、強さ、権力等、金銭等、人間の力を誇るなら、神と何の関係もなくなる。人が自分の努力によって生きようとするなら、神の愛を拒絶することになる。
沖縄の高校生が詠った歌、「灰色の檻」「儒艮(じゅごん)の墓」という暗く重たい言葉を用いて、そこに自分たちの毎日、日常があることを語っている。それは、主イエスが「自分の十字架を取って」と言われた、十字架そのものを指し示そうとしているのではないのか。その十字架から私たち、目を反らすことが出来るだろうか。