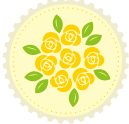
クリスマスおめでとう。また今年もクリスマスに巡り合うことができた。皆さんは「クリスマスらしさ」を一番、何に感じられるか。ツリーやイルミネーションなどの飾り、ケ、ーキやチキンなどの食べ物、サンタクロースのプレゼント、聖書のクリスマス物語などなど、皆、クリスマスをあらわす表現である。牧師だから、「聖書抜きにクリスマスはない」と喝破したいところであるが、やはり聖書以外のものがなかったら、いささか寂しい気がする。私はやはり「歌、音楽」が最もクリスマスらしさか、と感じる。「きよしこの夜」を歌い、「シュワキマセリ」を歌わないことには、クリスマスはやって来ない。幼稚園時代に教えられた刷り込みかとも思うが、野宿していた羊飼いへの、天使のお告げも、歌であったことから、最初からクリスマスは音楽に彩られている。なぜか。
「数や絵、文字のない文化は存在しますが、音楽のない文化はないのです」(ジョン・D・バロウ)。なるほどそうかと思わされる。こんな話を聞いた。ジャズ奏者の坂田明さんは、ボランティアで耳が聞こえない人たちの施設へ行き、サックスを吹く。音色が分かるはずもないのに、みんな熱心に耳を傾け、演奏が終われば「素晴らしかった」と拍手を送ってくれるのだという。音楽の感動を分かち合うのは、決して音だけではないのだろう。人の共感する力を知る。仏教の世界には「同苦同悲」という言葉があるそうだ。人々と一緒に苦しみ、一緒に悲しむ。それが一つの連帯を生むのだという。これも当世風に言えば、共感する力だろうか(佐賀新聞11.12)
耳の聴こえない方々が、音楽を楽しむ、おかしいと思われるか、不思議だと思われるか。実は私たちは、音楽をただ耳だけで聴いているのではない。目でも味わい、身体(振動)でも味わい、いわば全身全霊で味わっている訳である。クリスマスらしさの一番が、音楽というのも、クリスマスを身体全体で味わっているということではないのか。
今日のクリスマス礼拝は、まだアドヴェントのさ中である。まだ「待つ」時なのである。だから聖書の個所も「旧約」となる。新約のイエスのお誕生の話を聞きたい方は、イヴ礼拝に来たれかし。ゼカリヤ書である。この小さな預言書もアドヴェントで必ず読まれるテキストである。ゼカリヤは、バビロン捕囚後に活動した預言者とされている。バビロニア帝国がペルシャによって滅ぼされると、ペルシャの王キュロスは、捕囚のユダヤ人たちに故郷への帰還を許し、エルサレムに新しい神殿を再建するために資金提供をすることを申し出る。ところが捕囚後50年経過し、バビロンに生計を得て、すでに生活の根を下ろしていた捕囚民の腰は重く、なかなか故郷に帰還しようとしない。詩137編に、捕囚となった人々の歌が伝えられている。彼らはバビロンで、自分たちの故郷の歌を、大声で歌えなくなってしまっている。現地の人間にからかわれるからだ。歌を堂々と歌えない、クリスマスに歌がなかったなら、モチヴェーションは大いに下がるだろう。その落ち込んだ人々の心を鼓舞し、故郷に向かって出発する決断をどうにか促したい。そこで8つの幻ヴィジョンを語り、気力と希望を示そうというのである。ヴィジョンの提示によって、モチィベーションを上げようという、非常に現代的な発想がゼカリヤにはある。
預言者は11節にこう呼びかけている「バビロンの娘となって、住み着いた者よ」、かつてはエルサレムの都、そこに住む民は「シオンの娘」と呼ばれた。かつては、シオンの丘の上に、高く美しく装われる町がエルサレムであったのに、今ではその町の住民は、砂漠の茶色の町、低地バビロンに暮らす捕囚民となった。「かつて、わたしはお前たちを吹き散らした」。神によって、聖書の人々はごみのように吹き散らされた。彼らにとって、正直な所、心の底にあったのは、自分たちは神に捨てられた、ごみくず同然の存在だという抑圧的な思いであった。選民、神に選ばれた民、という高い誇りは、それが踏みにじられた時に、却って重く自分たちにのしかかったのである。
「命を保つ」、ということだけなら、雨風をしのげる場所を確保し、水や食料を手に入れ、その日をしのいでいくなら、何とかなるかもしれない。今年の台風で被災した方の様子が伝えられている。「顔なじみがいない日常は、取り残されたように心細い。避難所の閉鎖などに伴って地元を離れ、仮設住まいに移って暮らし始めた被災者だ。心情を察すれば心配が募る。台風19号は人と人をつないでいた地域の糸を断ち切った。長野市豊野町の79歳の男性は地区外にできた応急仮設住宅に引っ越した。周りの23世帯を回ったが知り合いはいない。近所同士で暮らした避難所は互いの境遇を語り合いつつ家族同様に付き合っていた。そのつながりが今はない」。
かつてのつながりを、まったく失ってしまった時に、人は自分が一人取り残されたように、捨てられたように感じるのである。つながりの中で生きるのが人間である。「互いの境遇を、語り合いつつ家族同様に」、それが風に吹き散らされるもみ殻のように、ばらばらにされたというのである。そして人と人とのつながりの根本に、神とのつながりの中で生きてきたのが、聖書の民なのである。彼らのつながりの喪失の根元には、神とのつながりが、失われているのである。
バビロン捕囚に至るまで、聖書の民は、常にまっとうに生きてきたのではない。さまざまに神の前に罪を犯し、過ちを繰り返しつつ、歩んできた。その度に神に叱られ、痛みを負い、悔い改めてゆるされて生きたのである。神とつながっていることで、立ち帰り立ち直ることが出来た。それは神殿という目に見える形で、神が共に居られることを実感できたからである。ところが今は神殿は全く打ち崩されて、異教の町で、異教の神々のいます神殿の間に、とぼしく暮らす身の上なのである。もはや私たちの神は、おられない。私たちは見捨てられた、何の値打ちもない。バビロンに暮らす聖書の民の一番の問題はそこにあった。そこにゼカリヤは、神の言葉を告げるのである。
14節15節「わたしはあなたのただ中に住まう」。「住む」という漢字は、火を灯す燭台のかたちが元になっているそうである。人が住んでいれば、明かりが点されるから。神の灯りが点されるのである。そして日本語の「住む」とは「水が澄む」とか「ことが済む」とか、「バタバタせず、安心して、落ち着いて、そこに座っている状態」を表している。そして何より、「共にいる」こと、なのである。神殿がなくても、たとえ故郷が荒れ果てて、打ち捨てられていても、風に吹きはらわれたもみ殻のようであっても、あなたのいるところにわたしは居る、と神は言われるのである。
神殿ならばそこに神はおられる、人間の常識である。ヘロデの宮殿ならば、そこに王はおられる。人間の発想である。ところで「馬小屋」ならばどうか。「かいばおけ」ならばどうか。そこに神はおられるだろうか。「わたしはあなたのただ中に住まう」と主は言われる。
掘っていた井戸で事故が起きた。地元のアフガニスタン人作業員が死亡している。非政府組織代表の中村哲さんが作業員の村を訪ねると、高齢の父親は悲しみを押し殺して言ったという。「こんなところに自ら入って助けてくれる外国人はいませんでした。息子はあなたたちと共に働き、村を救う仕事で死んだのですから、本望です…泉が涸(か)れ果て、小川の水も尽きたとき…あなたたちが現れたのです」(著書『医者井戸を掘る』)「人の望みの尽きる所、なお主はいまし、治めたもう」、「あなたがたの」ただ中に住まう」という主がおられる。