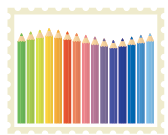
「学校で学んだ勉強を、全て忘れてしまった後、それでも残っている事柄が教育である」という定義がある。確かに、この年齢になると、学校で学んだこと、特に教科書の文章など、ほとんど忘れてしまっている。それでも本当に一つか二つ、今でも時折、思い出す学びがある。そのひとつは、国語の詩の授業で、担当教師はといえば、教科書の詩を簡単に解説した後、自分がオリジナル教材として作成したプリントを用いて、授業をしてくれた。そこで紹介されていた詩の一節、「イエスは、きっと声の大きな方だったろう…そういう人をわたしは尊敬する」というような章句が、なぜか今も心に残っている。誰の作品か、そして詩の全文は記憶していない、だがイエスの個性が、鮮やかに切り取られたように感じたのだろう。その教師が、キリスト者だったかどうかは、今は知る由もない。
もうひとつ、「倫理」の教科書に、「イエスの宗教思想」という単元があり、その特徴としてこう記されていたことを、憶えている。「イエスは、『悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる』という神の大きな愛(アガペー)を教えたが、同時に『あなたの手が罪を犯させるなら、その手を切り捨てよ』という厳しさを併せ持っていた」と。まだ洗礼を受けておらず、教会にもほとんど行かなかった頃の思い出であるが、こんな小さく些細な学びの中にも、今につながるきっかけが含まれていたのかもしれないと思うと、不思議な気持ちになる。
今日の聖書の個所は、いくつかの主のみ言葉の断片が、切り貼りされているような構成となっている。最初に主イエスによって、公生涯が十字架に帰結することが語られる。「人の子は、人々の手に引き渡され、殺される。殺されて三日の後に復活する」。それに続いて「いちばん偉い者」、「逆らわない者は味方」、「罪への誘惑」といった教説が語られる。これらの断片は、それぞれ独立した伝承であり、文脈的には互いに無関係に見える。福音書を記したマルコは、ただ機械的に断片を並べたに過ぎないのだろうか。
33節以下の「いちばん偉い者」の伝承を読むと、初代教会で、実際にこういう議論が行われていたらしいことが、すぐに想像される。最初に誕生した教会と目される「エルサレム教会」は、いわゆる12弟子を中心にして構成されたと思われるが、一番弟子シモン・ペトロが使徒の中でも一目置かれ、ヤコブとヨハネらが、それに続くと見なされていたようである。しかし程なく、12弟子ではなかった「主の兄弟ヤコブ」が中心的な人物として頭角を現したらしいのである。やはり「身内」の力なのだろうか。家族ならば、数年間の公生涯以上に、いろいろ主イエスについての密かな「情報」を得ていると思われたからなのか。パウロが「かつてはキリストを肉によって知っていたとしても、今はもうそのような知り方をすまい」(2コリント5:16)と強く語る言葉の背景には、そうした事情が反映しているのかもしれない。
マルコ福音書が成立した当時の教会は、まだ年若く、小さな群れでしかなかった。建物も大伽藍がある訳ではなく、何とか大勢が集まれる家屋を借りて、集会や礼拝を守っていたことが想像される。しかも紀元70年に勃発したユダヤ戦争のあおりを受けて、エルサレム教会は消滅するのである。そんな中でも弟子たちは「誰が一番偉いか(大きいか)」を議論しているのである。その時に主はどうされたか。36節以下「そして、一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。『わたしの名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は、わたしを受け入れるのである。わたしを受け入れる者は、わたしではなくて、わたしをお遣わしになった方を受け入れるのである。』」。「子どものひとり」に目を向け、その小さい存在を「受け入れる」ことを求めるのである。
38節以下の段落では、「一杯の水」が問題にされる。41節「はっきり言っておく。キリストの弟子だという理由で、あなたがたに一杯の水を飲ませてくれる者は、必ずその報いを受ける」。「ただ一杯の水」の施しで充分だというのである。もちろん、水道の完備した幸いなこの国のようでなく、毎日、井戸に出かけて水がめに水を汲んでくるというのは、大変な重労働で、飲み水は今とは比べ物にならない程の、貴重品であることに間違いはない。それでもたかが「一杯の水」なのである。神の国につながるのは、それで十分だというのである。
そして42節以下、「わたしを信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首に懸けられて、海に投げ込まれてしまう方がはるかによい」。この段落では最も直接的に「小さな者のひとり」が問題にされるのである。「つまずかせる」とは、原語では「(悪意をもって)落とし穴を掘る」というような意味合いである。いつも誰かのあらさがしをして、失敗したらその人を貶め、ひたすら自分の優位を保とうとするような姿勢のことである。問題は「わたしを信じる」という信仰の世界においても、そのような「落とし穴」が掘られることにある。
だからそれに続く「あなたの手が罪を犯すなら、あなたの目が罪を犯すなら」といういささか厳しすぎる印象を与える章句も、前述した「塵と梁」のたとえに関わる警句であるだろう。自分の目の梁には気づかないで、人の目の中の塵にばかりこだわり、批判や攻撃をするのである。もし徹底的に誰かを憎み、誰かをやっつけたいと思うなら、まず為すべきことは。自分自身の悪い所を全てぶった切って、すべて良い所になってから、行うべきではないのか。しかしそんなことをすれば、相手ばかりか自分自身もまた、無事ではいられないだろう。そこまでして誰を攻撃するのか。
だから主イエスはこう結ばれる。「あなたがたは何によって塩に味を付けるのか。自分自身の内に塩を持ちなさい。そして、互いに平和に過ごしなさい。」塩は平凡なものだ。色は白く、周りに溶け込み、味をつけ、味を調え、味を柔らかにする。そしで自分自身は形を失くすのである。
今、世界は「小さな者のひとり」をまったく無視して、強大な覇権にばかりに気を取られ、暴力に邁進している。主イエスは「あなた方自身の内に塩を持て」と諭される。その「塩」とは、主の担われた十字架、そこで流された血潮である。もう一度、主イエスのみ苦しみが何のためであったのか思い起こしたい。神の国は、どんな領土よりも、豊かな広がりを持っていることであろうか。