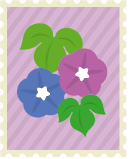
酷暑の日々が続いている。バテるから練習中は水を飲むな。クーラーは身体に悪いからつけるな。真っ黒になるまで日焼けをすると、冬風邪を引かない等など、私の子供時代の勧めである。
真夏に太陽の下で運動し汗をかく、それが身体と心の鍛錬となる、と教えられた。ところが今では真逆のことが教えられる。どんな時でも、水は十分に取る。暑さを我慢しないで、エアコンをつける。出来るだけ外出しないで、家の中で寛ぐ。気象庁によれば、日本の平均気温は、1898年(明治31年)以降では100年あたりおよそ1.1℃の割合で上昇しているそうである。昔、真夏になると「我慢大会」なる企画が催された。どてらを着て、布団をかぶり、炭を起こした火鉢にあたる。最後まで我慢できる人が優勝。今はそれが流行らないのは、そんなことしなくても、日本全国の夏は、我慢大会だからである。摂氏41度は、人の体温を遥かに超え、体温で言えば、生命の危険の迫る温度に等しいのである。
今日はヘブライ人への手紙から話をする。有名な個所だが、「主の鍛錬」と言う言葉が出来てくる。旧約聖書、箴言からの引用である。新約聖書の時代、旧約聖書の中で「箴言」は人気のあった書物だったという。諺のように、一節短く、覚えやすく分かりやすくかったためだろう。親や年長者が、若者に教え諭すのに、はなはだ便利だったからだろう。しかし「鍛錬」それも「主の鍛錬」とは、どういう意味のことを言おうとしているのだろう。
ヘブライ人への手紙は、紀元1世紀末頃記された、新約では比較的後期の書物である。ローマ帝国の版図は、最大となり、ユダヤ戦争によって、ユダヤの国は壊滅させられた。3節「罪人たちの反抗」つまり「謂われない悪口、ヘイトスピーチや暴力」という迫害はあるにはあるが、キリスト教はある程度人々の認知を獲得し、異邦の世界各地に、ひろく教会も点在する時代である。終末の待望はあるにしても、それはまだまだ先のことという感覚で、キリスト者達が今を暮らしている時代である。そこで何が問題であったか。
3節に「気力を失い疲れ果ててしまう」という言葉があるが、当時のキリスト者の状況や有様を的確に表現している言葉であろう。「耐え間ない苦労によって(長時間残業のように)、疲労困憊し、吾を失い、元気が無くなり、立ち往生してしまう」。この状態は、今、この国で盛んに注意・警告されている「長時間労働」や「熱中症」の有様のようである。
ところがこの言葉、大分、原意とはずれた表現である。ある解釈者は「たるみ、倦み」と訳している。心がゆるんでしまう。精神の弛緩、緊張感が無くなってしまうこと。そして「倦み」、やる気がなくなってしまう、嫌気が差してしまうということである。信仰的に、気を張って生きてきたが、次第に慣れてきて緊張感が緩み、実感が無くなってしまった、やんぬるかな、どうでもいいやという気持ちになってしまっているというのである。本当の危機は、外側にではなく、内側から来るものである。かのローマ帝国も、国家規模が膨張し、最大版図になった時に、内側からの崩壊を始めるのである。その要因は飽食と倦怠にあったと言われる。
そこに「主の鍛錬」というみ言葉が語られるのである。「鍛錬」という用語からどんなイメージを持たれるか。厳しい、鞭打ち、忍耐、がまん、努力、血の汗流し、涙を拭かない、という感じであろうか。オリンピック・アスリートが口にする「0.1秒を削り出す」などという言葉に、その意味合いがよく表れているだろう。「鍛錬」と訳したのは、その前節で、「罪と戦って、血を流すまで抵抗したことが無い」という文言に引きずられた感がある。これは古代の拳闘、ボクシングが意識されている。しかし、プロのボクサーでさえ命がけのスポーツであり、この時代は素手で打ち合ったから、普通の人間は、とてもではないか「鍛錬」の前に、死んでしまうだろう。
この用語は元々、親の(特に男親の)しつけ、を意味する言葉である。「鍛錬」と訳すと、聊か意味合いが強すぎる。「鍛錬」では、今日「虐待」のように受け取られ勝ちである。本来この語は「しつけ」を意味する言葉で、後に「教育」を指すようになる。当時は一般的な学校教育制度があったわけでは無いから、厳密には「家庭教育」を指す用語であった。難しく「薫陶」と訳されることもある。香をたいて薫りを染み込ませ、土をこねて形を整えながら、高価な陶器を作り上げる意から生まれた用語である。
さて男親が行うしつけ、ここには今、あるいはかつて、「男親の役割」を果たして来た、または果たしている方々がいる。ご自分の「しつけ」、の内実はどうだったであろうか。「鍛錬」であるか「薫陶」であるか。おそらく殆どの方は、「鍛錬」「薫陶」には遥かに及ばない、「しつけ」すらも覚束ない、と感じられるであろう。
山本周五郎の短編小説に『修業奇譚』という作品がある。文武両道で、血の気の多い若侍、主人公の河津小弥太は、いささか傲慢で、他人を馬鹿にしているのが玉に瑕。腹を立てると闇雲に通りががりの者を投げ飛ばす始末である。彼のこの困った性格をどうにかすべく、許婚が一計を案じ、一無斎という名のひとりの老人のもとで修業することになる。それは、毎日、薪を割らされ、縄やむしろを作るなど雑用ばかり。谷川で魚を掴み取りするように命じられ、溺れて死にそうになり、あるときは、上から石が落ちてよもや下敷きに、また五寸釘を踏み抜いたり、師匠がくれた木の実の毒にあたって寝込んだり。そこで師匠は言う(彼はただの炭焼きの老爺なのだが)。「人間にゃ誰にもかなわないことがあるだが、五人力で武芸の達人ちゅうおめえにも、やっぱりかなわねえことがあるだなあ」。山から下りて来た彼は、一人で立つこともできぬほど衰弱し、許婚に介抱され、世話を受けて、ようようのことで体力を取り戻す。これ以後、彼の生き方が変わる。「人間、やっぱりかなわねえことがある」。
「鍛錬」とは、ただ厳しく鍛え、強くなり、誰にも負けぬ力や精神力を身につける、それだけでないことが分かるのではないか。先の小説だが、彼の場合、己の弱さを知ること、人の愛を知ること、そこで人間のまことの絆が保たれていることを、発見したのである。それこそが彼の鍛錬であった。
「鍛錬」の原語「パイデイア」は第一に「しつけ」を意味する。親のしつけのことである。皆さんは親から厳しくしつけられただろうか、また子供を厳しくしつけただろうか。「しつけ」は子供のためと言いながら、実は親が楽をするためなのである。だから大抵のしつけは、身に付かない。しかし本当に子供が影響を受ける、身になるしつけがある。よく言われるではないか。「子供は親の背中を見て育つ」。正真正銘のしつけ、パイデイア、鍛錬は、実に「後姿」なのだ。
主イエスは言われた。「わたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を取って、わたしに従いなさい」。「自分を捨て、自分の十字架を取って」とは、余りに無理難題のように響く。ところが、み言葉をよく読んで欲しい。「主イエスについて行く」ことがまず第一なのである。つまり「主の後姿を見て歩むなら」、自ずと自分を捨て、自分の十字架を負って生きることになるよ、生きられるよ、というのである。「主の背中に従うなら」、ここにパイデイアのすべてがある。
河津小弥太の鍛錬は、実は、高慢で人を小馬鹿にし、腹が立つと誰彼かまわず投げ飛ばす自分と、和らぐことにあった。師匠とは言え、ただの炭焼き老人の背中が、それを教えた。弱さを知ることで、自分の内に「平和を結ぶ実」を実らせたのである。私たちも同じであろう。主イエスの背中によって、そのパイデイアによって、自分の内に「平和を結ぶ実」を実らせるのである。