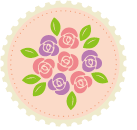
「秋の日はつるべ落とし」と言われるように、11月を迎え、昼の短い季節となった。夕方薄暗くなるのが早いので、火影の恋しい時でもある。こういう文章を読んだ。
数年前の夏、故郷北海道の様似に帰省した。夕食を終え、ぼんやりと星空を眺めていると、久しぶりに夜の山へ入ってみたいという衝動が沸き起こった。人家の灯に邪魔されずに、夜空を眺めてみたいと思ったのだ。山あいの道を、行けるところまで車を走らせる。エンジンを切り、ライトを落としたとたん、漆黒の闇に包まれた。突然の闇の出現に戸惑い、肌が粟立つような恐怖を覚えた。長い都会生活の中で、夜の暗さをすっかり忘れていたのだ。月はなく、空には満点の星がきらめいていた。月明かりとは違い、星の光は周りを照らしてはくれない。原始の闇が広がっていた。漠とした夜気に乗って、森の中から甘酸っぱい香りが漂ってくる。懐かしい夜の匂いだ。虫の声にまじって、意表をつく鋭い鳥の声。ビクッとして立ち止まり、そのたびに懐中電灯を向ける。光が届く距離ではない。そろそろ戻ろうかと思いつつ足を進める。不意に出現する何かに怯える。動物よりも人が出てくる方が怖い(小山次男『闇に包まれて』)。
「真っ暗闇の中で、動物よりも人間の方がこわい」、現代に生きる私たちにとって、確かにそうかもしれない。人間は何をするか分からない。つくづくそんな事件がニュースで伝えられている。
今日は創世記15章アブラハムの物語の一節から話をする。「神の約束」という表題が付せられている。聖書学では「アブラハム契約」と呼ばれる個所である。旧約聖書、新約聖書の「約」の字は、「契約」の意味である。新約は主イエス・キリストの契約、十字架に付けられる前の晩、最後の晩餐の席上で「これはわたしの血による新しい契約である」という言葉に由来する。他方、旧約には、さまざまな神との契約の場面が語られている。ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、ダビデらと神が交わした諸々の「契約」が、繰り返しいくつも語られている。
今日の個所では、古代の契約の流儀が詳細に伝えられている。9節以下「主は言われた。
『三歳の雌牛と、三歳の雌山羊と、三歳の雄羊と、山鳩と、鳩の雛とをわたしのもとに持って来なさい。アブラムはそれらのものをみな持って来て、真っ二つに切り裂き、それぞれを互いに向かい合わせて置いた。ただ、鳥は切り裂かなかった』」。次いで17節「日が沈み、暗闇に覆われたころ、突然、煙を吐く炉と燃える松明が二つに裂かれた動物の間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで言われた」。
契約を交わす際には、犠牲の動物を裂いて、祭壇の上に吊るす。そして契約をする者同士が、連れ立って、その犠牲の供え物の血が滴る間を、共に歩むのである。一説に、もしどちらかが契約に違反すれば、この供え物のように八つ裂きにされてもかまわない、という象徴行為だという。だから契約を「交わす」という言葉は、原意は「切る、裂く」という言葉が基になっている。福音書でも、主イエスもまた、自らの体を裂いて、血を流し、私たちと契約を結ばれたのだ、という理解がなされている。
但し、アブラハム契約は、非常に理想化された契約であると言えるだろう。普通なら「契約」は相互に守るべき事柄を一つひとつ書面に記し、両者が確認、了承のサインをして、共に契約のしるしとして祭儀を執り行うのが、通例である。しかしアブラハム物語の「神の契約」は随分、異質な形態をとっている。神が一方的に、アブラハムへの恩恵の付与を宣言し、大いなる祝福を与えるのである。1節「『恐れるな、アブラムよ。わたしはあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう』。」そして5節「『天を仰いで、星を数えることができるなら、数えてみるがよい。あなたの子孫はこのようになる』」。これに対して、アブラハムには何らの義務をも命じられていない。何という大盤振る舞いであろうか。ただ「アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた」と記されるのみである。
そもそも「契約」とは、双方の守るべき義務、と与えられる恩恵。御恩と奉公とが明らかにされて、初めて成立するものである。この契約は、契約とはいうものの、神の独り芝居のような、一方的な恵みの付与、恩恵の授与である。裂かれた動物の間をくぐる契約儀礼も、神だけがそのように振舞っている。この時アブラハムは、何と眠っているのである。しかしこの契約は、主イエスが十字架によって明らかにして下った「新しい契約」の先取りともいえる伝承である。人は神の恵みに対して何も為し得ない、決して返礼をすることは出来ず、有難くその一方的な恵みをいただくしかない、ということである。それこそ「信じる」ということに他ならない。そしてその恵みは、眠ったところでもたらされる。「眠り」とは、人にとって最も無防備で、安心している状態でなされるものである。
もう一つ。今日の個所で興味深い点は、この恵みの契約が、夜、闇の中で成されているということである。12節「日が沈みかけたころ、アブラムは深い眠りに襲われた。すると、恐ろしい大いなる暗黒が彼に臨んだ」、さらに17節「日が沈み、暗闇に覆われたころ、突然、煙を吐く炉と燃える松明が二つに裂かれた動物の間を通り過ぎた」。「恐ろしい大いなる暗黒、暗闇に覆われる」という表現は、古代の夜の有様を端的に表現しているであろう。「鼻をつままれても分からない」という日本語のユーモラスな言い回しがあるが、光の全く見えない闇にひとり置かれるということが、どれ程の恐れを呼び覚ますだろうか。「そろそろ戻ろうかと思いつつ足を進める。不意に出現する何かに怯える。動物よりも人が出てくる方が怖い」。何がやって来るのか、皆目見当がつかない。
しかしこれは人生行路においても同様である。現実に、夜の真っ暗闇の中に置かれるということばかりでなくて、これから私の歩む人生の道がどうなるか、人間の力では、決して見通せないのである。実際、神はアブラハムに、その子孫がエジプトで奴隷として苦しむことを不気味にも予告をしているのである。人間はまったく未来を知る由もない。それこそが、「恐ろしい大いなる暗黒、暗闇に覆われる」人間の営みなのである。だから人間はその闇の中で呻き、手探りで、身体を伸ばし、不安を抱えて一歩を歩みだすしかない。
しかしアブラハムが告げられたように、大いなる恐ろしい暗闇の中で、自分を見つめていてくださる方がおられ、出会ってくださる方がおられるのである。そしてその方は、くらやむ井の中で呻く私に、恵みの約束をもって導いてくださる、というのである。「恐れるな、アブラハム、わたしはあなたの盾である」。
作家五木寛之氏が『朝顔は闇の底に咲く』というエッセーを書いている。その中に、中学生の頃から朝顔日記をつける生物学好きの少女(貝原純子氏)のことが紹介されている。この方は高校・大学と生物学を一生懸命学び、卒業した後も朝顔の研究を続けているという。彼女の疑問は「どうして朝顔は朝になって、あの大輪の花をきちんと咲かせるのだろうか」と言うことだった。それは、気温の変化のせいであろうか、光のせいであろうか、いろんな方法で実験するのだが、なかなかわからない。ずっと一定の温度の中に置いても、あるいは四六時中光を与えつづけていても朝顔のつぼみはなかなか開かなかったのである。
その後も研究を続、彼女はこのような仮説を考えたという。「アサガオの花が開くためには、夜の暗さが必要なのではないか」。つまり、アサガオが朝開くのは、夜明の光とか暖かな温度のせいではない。夜明け前の、冷たい夜の時間と闇の濃さこそが必要なのだ。アサガオは夜の闇の中で花を開く準備をするのである。
私たちは、光り輝く神の栄光の前に立つことは出来ない。罪ある人間は、それに耐えることができない。自分の抱える闇、暗さの中でしか、神に出会うことは出来ない。煌々たる灯りの中で、すべてが白日の下にさらされるなら、誰も耐えることは出来ないだろう。クリスマスの音信が届けられたのも、「夜、羊飼いたちが野宿している」時である。夜闇の中に、すべての民に与えられる、喜びの音信は伝えられるのである。