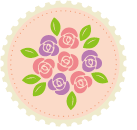 こんな話がある。縄文時代のある遺跡から人骨が出土した。年齢は十五歳程度の女性の人骨であった。おそらく小児麻痺を患ったのだろう、手足の骨が細く、とても華奢だった。労働には適さない。しかし、彼女はたくさんの貝製の腕輪をはめ、首飾りをして葬られていた。ここから皆さんは何を読み取るか。
こんな話がある。縄文時代のある遺跡から人骨が出土した。年齢は十五歳程度の女性の人骨であった。おそらく小児麻痺を患ったのだろう、手足の骨が細く、とても華奢だった。労働には適さない。しかし、彼女はたくさんの貝製の腕輪をはめ、首飾りをして葬られていた。ここから皆さんは何を読み取るか。
古代、貝でできた装飾品は、ぜいたく品で、普通の人がふんだんに身に着けられるものではない。考古学者はこう読み解いた。おそらくムラ(共同体)の巫女として、神々と交わる聖なる役割を演じていたのだ。少なくとも、彼女はその身体の障がいゆえに、生存を拒まれたり、疎んじられることはなかった。短い生涯を、いわゆる肉体労働には関わることはなかったろうが、しかも普通の人には許されぬ、聖なる役割をもって全うしたのである。
「(古代の)生命観では、命あるものに有用/無用といった区別はなかった。そうした思考を退ける。だから、役立たずな人も、役立たずな物も存在しない。きっと、役立つ人ばかりでは社会は暴走して、やがて壊れてしまう。そんな役に立たぬことを考える時間を大事にしたい(赤坂憲雄・北方風土館館長)」。
さて、今日の聖書の個所は、マルコ3章20節以下の段落である。まず21節「身内の人たちは」と語られる。31節では再度、身内の人間が登場するが、「イエスの母と兄弟たちが来て」と「身内」とは誰なのか、がより具体的に、説明されている。同じ事柄の記述が繰り返される、というのは、この福音書の著者マルコが、あえて意図的にそういう書き方をしている訳で、やはり「強調」ということだろう。節の後半には、「『あの男は気が変になっている』と言われていたからである」という風に、身内の人々がやって来た理由が説明されている。
「気が変になる」という訳語には、翻訳者の苦労が偲ばれる。「エクセステー」というギリシャ語が使われているのだが。この言葉は英語の「エクスタシー」という単語の語源である。原形は「エクスターシス」と言い、「自分の存在から外へ出てしまう」という意味あいの言葉である。だから英語の聖書はそのまま直訳している場合が多い。“out of mind”
つまり、「自分の外に出てしまう、我を忘れる、我を失う、恍惚状態になる」というような意味を表している。「外に出る」、主イエスの生活の実際はその通りだった言える。
おそらく主イエスは、母マリアはじめとする家族の中で、「大黒柱」のような存在であったことに間違いはない。壮年と言える年齢になるまで、家族の生活を支えてきた。ところがいつの頃かナザレの家を離れて、家出して、バプテスマのヨハネの宣教活動に関わり、ヨハネがヘロデに捕らえられると、今度は、自ら弟子たちを集め、「神の国」の宣教活動を始めてしまった。家出したまま帰って来ないのである。まったく家族の生活のことを顧みず、自分たち身内のことを忘れて、病人を癒し、貧しい人のケアをし、つまり他人のことばかり面倒見て、神の国の宣教をしている、まさに「エクスターシス」だ、「はずれ者」だというのである。
但し、家族の者たちは、主イエスの宣教そのものを「おかしい、気が変だ」と考えたのではないだろう。そんな「宣教活動」のような胡散臭い仕事ではなく、もっと手堅い大工として働いてほしい、という訳ではない。当時、宗教活動をする者たち、例えば律法学者がわんさかといて、方々で人々に教えを垂れているのである。だが、どうせするなら、ナザレの自分の家を根城に、そこに腰を据えて、皆が集まって来るような営業をしたらよいではないか、というのである。家族の者たちにとって、家出して、自分の方から出向いて行って、赤の他人を尋ねて巡回する、という振る舞いをなぜするのか、どうしても理解できなかったのである。
今日のテキストの要は、「身内の無理解」という点にある。マルコは、主イエスの身近にいた人々の無理解という神学的主張を、福音書を通して底流のように語るのである。今日の段落には、身内の人々の無理解に続いて、今度は「律法学者(ラビ)」の無理解が語られている。主イエスが行う癒しのわざを、「ベルゼブルの力」だと言い立てるのである。悪口を言おうとするなら、何でも難癖は付けられるものである。そもそも律法学者(ラビ)とは、主イエスの同業者で、神の言葉を人々に教え、その真心を伝える仕事である。そうした主イエスと身近なところにいた人々が、主イエスのことに無理解なのである
確かに生活を一にする家族や近親は、世間には知られないプライベートな身内の様子を、いつも目の当たりにして生きることになる。だから内と外との落差に、「つまづく」ということが起こる。あるいは「自分のことは棚に上げて」とか、良い所は見えず、悪いところばかりが目に付く、ということにもなる。「相手の目の塵は見えるのに、自分の目の梁には、気づかない」のである。ところがマルコは、確かに主イエスの家族、身内の無理解を語り、同業者であるファリサイ派の人々の無理解を語り、ついには宣教活動の中で最も近しい場所にいた弟子たちの無理解を、強調するのである。主イエスの近くに居た人々は、皆、主イエスのことを「まったく分かっていなかった」というのである。そして今の私たちにも、行間に問いかけているのである。「あなた方は分かっているか」。
皆さんは「分からない」とか「無理解」とかが、どうして起こると思うか。知識がない、浅くしか考えていない。本気で、向き合っていない、努力が足りない、どれも正解だろうが、最も根本に横たわる問題は、「事柄」そのものから目を反らしてしまうから、ではないのか。「事柄」そのものを見ようとしない、すると「無理解」が起こるものであるということだ。今まで散々病に苦しんで来た人が、主イエスによって癒された、それを知って、「これまで辛かったねえ、治ってよかったねえ」と素直に喜ぶことはできないのか。事柄によって判断する、受け止めるとは、そういう態度のことである。教会で、誰かが重い病に罹り、あるいは試練に打ちひしがれている人がいる、すると、皆の元気がなくなる。そしてその人々が恢復する、元気を取り戻す、とその当人ばかりか、他の皆も元気を回復する、ということがしばしば起こる。それは、教会が「事柄」そのものを受け止めるからなのである。規則や手続き、慣例云々をいう前に、悲しみや喜び、嘆きや赦し、人間には本来、負い切れない、「事柄」そのものを何とか受け止めようと、祈り、分かち合おうとするからである。
マルコの主張することも同じである。身内の人、身近にいた人々は、主イエスを理解しなかった、分からなかった、それは「事柄」を見ようとしなかったからだ、というのである。ではそもそも主イエスの「事柄」とは何か。それは「十字架」である。病む人を癒し、貧しい人々と共に食事をし、神の国の福音を伝えるという、主イエスの働きが行き着く先は、まさに十字架に架かり血を流されることであった。そのようにして神の赦しの愛が、すべての人の人生に表される。主イエスの歩みを、十字架という事柄から見ないならば、主イエスのまことを知ることはできないのである。
こんな文章を読んだ。息子は小さく生まれ、2回の外科手術を受けたが、大きな病気をすることなく、元気に成長している。発達はゆっくりで、当該年齢の子どもの約半分だが、確実に伸びている。障がいのある子どもの親になった時、これまで培ってきた常識は全く役に立たなくなった。息子の成長とともに、親として障がい受容を繰り返し、これまでの「普通」「常識」からほど遠い、新しい価値観を作り上げる、人生の再構築がスタートした。
息子の子育ては、自分の中にある「普通」と言う鎖が解け、新しい世界、価値観を広げていく作業。娘を育てていた頃には、気付くことのなかった、小さな喜びや驚きが、私の感性を豊かにしてくれる。子育てにはさまざまな悩みがある。だが、大抵の悩みは親である私の「普通」という呪縛から生まれる。その呪縛から解放された時、いろいろな悩みが一気に減った。それは、教育や社会活動でも生かされ、多角的に物事を見る視点にもつながる。「子どもは」ではなく「この子は」という視点で見ることができるようになったことは、私が障がいを持つ息子の親になった一番のギフトだと感じる。(比嘉佳代、おきなわedu代表取締役)。
「子どもは(子ども一般)」ではなく「この子は」という視点で見る。するとこの目の前の自分の子の負っている課題や困難がはっきりと分かるし、同時にこの子にしかない恵み、もまた見えてくる。それこそが「十字架」を見る、という姿勢である。「事柄」をそのまま見れば、すべての出来事に主イエスがふれていることに気づくであろう。主イエスの十字架を見ることは、自らが負う十字架を知ることである。