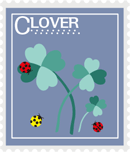
「やられたらやり返す、倍返しだ」という台詞で話題になったドラマがある。夏からセカンド・シーズンが開始され、大方の話題を呼んでいる。キャストに歌舞伎役者が多用され、いささかあくの強い、大仰な演技がドラマを盛り上げているようだ。このドラマは現代を舞台にしているものの、実のところ「時代劇」のような善悪のストーリー展開の分かりやすさで、人気を博しているとも言われている。権力をかさに着た悪人の理不尽な仕打ちに、痛めつけられながらもしたたかな知恵をもって報復する、という筋書きは、古代文学の典型的手法でもある。確かに、不条理に強者に虐げられている者が、一転、立場を逆転させ、相手をねじ伏せる、というのは、聞く人にカタルシス効果を与えるであろう。
聖書の世界を始めとする古代世界の、最も典型的な生活論理は、「倍返し」であった。冠婚葬祭時の宴席への招待や、報復(復讐)の際には、一方的に受けるだけでは許されず、お返し(返礼)する義務を課せられていたのである。それも相手からされた以上のお返しが、期待される、相手から要求されると言うよりは、立場を優位にするために、自分からそうするのである。それによって共同体成員の絆が強められ、富の再分配もなされる。だから生活のすべてが、「施し」と「返礼」によって組み立てられていると言って差し支えないだろう。
今日の聖書の個所では、主イエスがあるファリサイ派の議員から招待を受けて、食事の席(宴会)に連なる、という場面設定である。確かに主イエスは、様々な立場の人から度々食事の席に招かれ、そこに集まる人々に向かって語り、あるいは癒しのわざをおこなったと伝えられる。この個所に登場するファリサイ派の議員のような、ある程度の社会的地位のある人の招きならば、正式の招待であるから、なおさら返礼は欠くことの出来ない必須事項であった。主イエスの「語り」、そして「癒し」は、「招待」における「返礼」のようなものであったのだ。宴席は、飲み食いで親睦を深めるだけでなく、「名誉と恥」のせめぎあいの場であり、招待される者の人柄や人格が試される場所でもあった訳である。7節以下の「上席と末席」の話題や、12節以下の「宴会の招き」への心得は、この辺りの事情を端的に物語るものである。
最初に語られている「水腫の人の癒し」については、ファリサイ派の議員のしたたかさと狡猾さが背後に隠されている。その当日は「安息日」である。神の安息にあずかるため、一切の労働を禁じられる日である。宴席に招かれるということは、返礼の義務を免れない。他日に返礼の宴席を設けることは、主イエスにとってはできない相談である。だからその宴会の場で「返礼」として「癒しのわざ」が行われるのである。その場に連なっていた「水腫を患っている人」とは、議員の係累の内のひとりなのだろう。しかしその日は「安息日」である。一切の手のわざが封印される日である。「安息日」を守れば、「返礼」はできず面目を失い、人々からの評判を失することとなる。しかし何か「わざ」をすれば、「安息日」掟を破ることになる。そのジレンマの中に主イエスは置かれるのである。何と巧妙な駆け引き、そして嫌がらせを、この議員は画策したことであろうか。
たとえ親睦の宴席であっても、ちゃんと上座と下座があり、誰がどこに座るか、は非常に重要な問題なのである。これは古代だけの問題ではない。現代の国際会議でも同じことが腐心されている。どこの国が招かれるか、どこの国の代表が、どこに座り、誰の横に位置するか、それだけで国と国との関係の実情が、透けて見て取れるのである。かつてサザエさんの漫画の一コマで、波平氏は「失われつつある日本の美徳を守る会」のメンバーなのだが、その会の会合で、誰がどこに座るか、皆譲り合い、何時間たっても一向に座る席が決まらず、会が始まらないという場面が描かれていた。国際会議とは、正にそんなところですったもんだしているのかもしれない。
ユダヤ人にとって、「安息日」という厳格なルール、そして古代社会での「施しと返礼」という厳格なルールの狭間にあって、主はどのように振舞われたのか、そして教会はどのように世間に対するべきなのかを、このテキストでルカは見事に語るのである。まず「安息日」について、主は「安息日のために人間があるのではなく、人間のために安息日はある」と教え、神の律法が恵みの道であり、生命を得させるための掟であることを、強く主張したのである。そこから5節「息子や、牛が井戸に落ちたなら、安息日であっても、それを引き上げてやらないだろうか」と言われるのである。生命への集中こそ、主イエスの根源的視点であるだろう。
さらに「施しと返礼」については、13節「宴会を開く時には、返礼ができない人々を招け」と言われる。「お返しができないから、あなたは幸いだ」。返礼できないことが幸いであるとはどういうことか。福祉制度の未発達な時代である古代から、「施し」は、人としての当然の務めとして強調されて来た。ところがそれらは、「社会秩序」を維持する機能として、重んじられたのである。しかし「施し」の根本にある精神は、「返礼」というような見返りを度外視した「愛」にこそあるはずである。ここでも主イエスは鋭く根本的な視点を私たちに示すのである。「愛」を欠く「制度」によって、人間は抑圧され、あたりまえの「共に生きる」ことが歪められていることを、訴えるのである。
さいわい 幸い(さいわい)とは、その人にとって望ましく、喜ばしい状態、つまり幸せ、幸福のこと。 古語では「さきはひ」。 「さき」は、花が咲くの「咲き」であり、「はひ」は地を這うことの「這い」で、ものごとが地を這うように広がっていく様子を表している。
制度や決まりに縛られない自由な心こそが、幸いの源泉ではないか。花は決して誰かに見てもらおう、褒められようとしてさくのではない。動けない花に、自然と虫たちが訪れ、生命を助け、支え、新たに生命を生み出していく。そのように、私たちも「愛」と「生命」を生き方の中心に据えて、生き直すことが、悔い改めの本質であるだろう。
但し、この主イエスの深い言葉に、人々は、「押し黙り、何も答えなかった」、と言われる。これもまた現代に生きる私たちの問題を、端的に表しているだろう。たとえ非力であっても、何も応答しないことが、人間の問題なのである。主イエスへの応答は、非力であっても、私たちを無力にはしない。