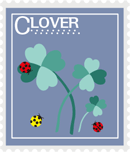
「暑さ寒さも彼岸まで」と言われるが、まだ残暑の日々が続いている。この夏も酷暑であった。皆さんの中で、暑さに対処する秘訣をお持ちの人はあるだろうか。例えば、暑さ対策ということで、いろいろ商品が売り出されている。今年は小さな扇風機を持って歩いている人を、しばしば見かけた。また日傘で、中に扇風機のついた商品も販売されている。涼しいのだろうか。寒がりとか暑がりとかいうが、実際に科学的データで、暑さ、寒さに強い人、弱い人があるらしい。この国の住民は、風鈴の音を聞くと、ほんの少し体温が下がる。外国の人はそうではない。文化とはそういうものだろう。さらに効果的なのは。ホラー映画を見ると、体感温度が4.6度下がる、とのデータがあるそうだ。
寒さ暑さばかりでなく、皆さんは自分が強い、と思っているか、それとも弱い、と思っているか。これ結構自分で考えるのと、人が見る目では違っていることがしばしばである。
この夏、三十年ぶりに「富弘美術館」を訪問することができた。前に観た時とは、建物自体も変わって、新しい美術館になっていた。もちろんそこに飾られている絵も、以前と比べて変化をしている。星野氏は依然として同じく、横たわり、絵筆を口で咥えて描いていることは変わりない。しかし、描く題材、詩作の傾向、そして線や色が、昔と随分違うのである。「描き始めた頃は首に力がなかった」と氏は回顧するが、「戦や色」の変化は、ただそれだけではないだろう。内面の変化か。『やぶかんぞう』という作品がある。「いつか草が/風に揺れるのを見て/弱さを思った/今日/草が風に揺れるのを見て/強さを知った」。これは実に星野氏自身の人生の表白である。身体が不自由になったことは、そのまま「弱く」されたということで終わらない。
人間の強い、とか弱いとか、どこではかったらよいのだろうか。こういう言葉がある。「人の強さには、倒れない強さと、起き上がる強さがある」。私たちはどうも「倒れない」ことを強さと信じる誤解があるようだ。「起き上がる」というのも、強さであることに、間違いではない。しかし、起き上がる前に、力を抜いて打ち伏している状態もまた、「強さ」ではないのか。「免振」、大きく揺れ動くことで、かえって崩壊の力を打ち消し、他に逃がす方法もある。
ただこんな見方も有る。「われわれはみんな他人の不幸を平気で見ていられるほどに強い。自分の不幸に耐えられるほどの強さはないが、他人の不幸に耐えられるだけの強さは、ほとんどの人が十分に持っている」(ラ・ロシュフコー格言集)。皮肉的過ぎるかもしれない。
荒井献という聖書学者が、以前、東日本大震災について、次のような発言をしている。「報道などを聞いておりますと、どうも違和感を感じることがありますね。一般の報道は「強い日本へ」「がんばれ」ということをしきりに叫んでいます。それに引っ張られる形で、キリスト者も「強く」「がんばれ」というメッセージを発信しているように思います。しかしこれらは少なくとも、私が考えるキリスト教のメッセージと全く違うものです。この「危機」に際してキリスト教が言えることは、「弱さを絆に」ということなのだと思います」。「危機」の時に、だからこそ「強く、がんばれ」とはよく言われることである。そういうときに「弱さを絆に」と言ったら「危機感がたりない」というお叱りを受けることになろう。「弱さを絆に」とはどういうことであろう。
今日はローマ書のみ言葉を共に学ぶ。今も昔も教会にはいろいろな人が集う。ローマの教会でもいろいろな立場、身分の人が集い、特に人間の強さ、弱さが問題になっていたらしい。1節「信仰の弱い人を受け入れなさい」。ここでは食べ物のことが問題になっている。肉を食べるか食べないか。どうでもいい問題と思うか。今は嗜好や健康の問題であろう。
しかし聖書の時代、何を食べるか、ということにも、弱さ強さが関わって来た。パウロは「野菜だけ食べている人は、弱い人」と言っているが「弱い」を「弱々しい、ひ弱な」というイメージで考えると、理解を損なう。「野菜」だけで我慢できる、というのは、強い精神の表われかもしれない。本来、強い弱いとは、人間の違い、一人ひとりがどうしようもないくらいに異なっている、ことに根があるのではないか。そして問題は、強さ弱さ、そういう決定的な違いを持つ人間が、それでもばらばらにならず、胡散霧消せずに、共に生きることがどうしたらできるのだろうか、ということである。パウロはそれを7~8節に凝縮して語るのである。
「誰一人、自分に向かって生きる人はなく、自分に向かって死ぬ人はいない。生きると言うのは、神に向かって生きるのであり、死ぬと言うのは神に向かって死ぬのである」。中世の教父アウグスティヌスは「人は神に向けて創られた。だから神のもとに憩うまでは、平安を得ることが出来ない」と語った。彼は、人間は皆、行くべき方向を持っている、というのである。かならず何かに向かって歩む続ける、生きる時も、死ぬ時も、だからその方向がはっきりしないと、平安を落ち着きを得ることが出来ない、というのである。行くべき目当てがはっきりしていれば、途中のプロセスを楽しむことができる。少しくらい迷っても、へこたれても、休みながらも何とか行きつくわ、と歩みを進めることもできるだろう。どこに向かってゆくのか、訳の分からない時には、途中を楽しむ余裕すらない。ただ右顧左眄するばかりである。人ばかり見ている、人の目ばかり気にしているというのは、本当の目標を持っていないからだ。
福音書の逸話に非常に興味深い記事がある。ガリラヤの湖で、イエスが弟子たちだけで、強いて船に乗せて先に行かせる。しかしひどい風が吹いて弟子たちがこぎ悩んでいるのを知って、イエスは海の上を歩いて、弟子たちに近づかれる。最初弟子たちは幽霊だと思い怯えるが、イエスだと知って大いに安心する。ペトロはイエスを見て、そっちに行かせてくれと懇願する。ペトロは海の上を歩いてイエスに近づくが、強い風に気がついて怖くなり、沈みかけ、溺れる。イエスをまっすぐに見ているうちは、荒れた海の上も自由に歩ける。しかしイエスから目をそらし、荒れ狂う波に恐れおののき、こころをとらわれてしまうと、とたんに波に飲み込まれるのである。
この逸話は、初代教会の人々の体験が色濃くにじんでいるであろう。イエスだけをまっすぐに見て、目をそらさない限りは、人間は荒れ狂う人生の中を自由に歩める。しかし周囲に気を取られ、イエスから目をそらせば、波に飲み込まれる。信仰者の強さと弱さを如実に語る物語だろう。ただ、慰めなのは、溺れかける私たちをイエスの方が手を伸ばしてがっしり掴んで下さると言うことである。それほど私たちはよそ見をする。それを掴んで下さる主がなければ、私たちはイエスを目指しては、とうてい歩むことが出来ないだろう。
私の恩師で、結婚の仲人をしてくれた人なのだが、つらく長い闘病生活の末に、亡くなられた方があった。一時期、小康を得て自宅で療養されていた。その時に訪問すると、先生がこういわれた。「わたしは病院のスタッフの方、医師や看護師から、物事に動じない、気丈な、強い人間だと思われていたらしい。文句を言わず、静かに痛みに耐え、声を荒げることがなく、いつも冷静な態度で過ごしている、と。しかし入院中、学校のこと、教会のこと、病気のことを考えると、不安で不安で、心配で心配で仕方なかった。どうしようもなくなった。だからいつもいつも勇気をください、勇気をくださいと神に祈っていた。今でもそれは変わりない」。人間の強さとは何か考えさせられる。強さとはどうも自分の生命の中からは出てこないものらしいのである。何者かと向き合うところから、その目を向けるところからやってくるものらしいのである。
「誰一人、自分に向かって生きる人はなく、自分に向かって死ぬ人はいない。生きると言うのは、神に向かって生きるのであり、死ぬと言うのは神に向かって死ぬのである」。人生行路という。どこに歩むべきか、聖書を読む私たちには、はっきりと示されている。だから道に迷おうが、それようが、遅くなろうが、道草を食いながらでも大丈夫である。かえって道草を食う方が、歩む道の楽しさを味わえるかもしれない。小さい時、楽しかった思い出はないか。顔をあげれば、そこにイエスはおられる。祈れば、主は手を伸ばして、私たちを掴んで下さる。要は神様のところに行きつく道を歩んでいるということである。これほどの安心はないだろう。