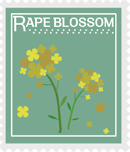
こういう文章を目にした。人間、へんな処で自慢するって事、ありませんか。「病気自慢」…これは、たとえば、「風邪で三日も寝こんでしまって…」なんて言うひとがいると、 「いやー、私なんか一週間もですよ」さらに、「もう一月も調子が悪くって…」という具合に、 より重症の人のほうが、偉いような状況に陥る事をいいます。別の例では、先だっての交通違反なんかでも、最後は罰金10万円が一番偉い様になってしまいます。
さらに…同じような事に、「貧乏自慢」とか「犯罪自慢」さらには「お風呂に何日も入らない自慢」…と言うように、本来自慢とは反対のことをついつい、自慢してしまう事ってありませんか。こう言って人に同意を求めつつ、実は私がその「反対自慢」が大好きです。ただ、そうやって「自慢」していられる間は良いのですが、実は本当に「ヤバイ」状態になると自慢どころではなくなってしまうのです。
人間は実にいろいろなネタで、「自慢」できるものだとつくづく思う。普通なら自慢できないような不名誉?な事柄を、あえて自慢の種にする、というのは、そこにユーモアやウイットをも感じさせられる。単に独りよがりの「自慢」だったら、周りで聞いている人にとっては、それこそ端迷惑に違いない。キリスト教でも「罪人自慢」というのがあるらしい。「わたしは罪人です」、「いやわたしこそもっと重い罪人です」、「いやあなたよりも、私の方が…」。とにかくこれ見よがしの「自慢」というものは、何であれどこか愚かしく滑稽で、見苦しく感じられる。しかし、「自己肯定感」と「自慢」はどこかで接しているところがあり、人に言うかどうかは別として、自慢できるものがある時、人は自分を肯定することができるのではないか。やはり人間は、どこかで「自分をよし」、とすることで生きているのである。
今日の聖書個所でパウロは、3節「わたしに与えられた恵みによって、あなたがた一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ、神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです」と語っている。ここでパウロが「自己評価」を話題にしていることが、非常に興味深い。「汝自身を知れ」、ギリシャのデルフォイのアポロン神殿に刻まれていた箴言だという。成程、古くから、人間は自分自身の真の姿を、正しく把握しようと努めて来たのであり、さらにこの文言に続けて「度を超すなかれ」とも記されていたという。パウロもまた当時の教養人として、こうした格言に親しんで来たことに間違いはない。
現代ではしばしば「自己評価」の重要さが取りざたされる。学校等でも、年に一度くらい「自己評価」が公にされる。それぞれの授業、学校行事や諸々の教育活動について、質や満足度が自主的に計られて、統計として数字で公表される。「教育内容」の是非や質を、「数字」として把握し、表現しようというのである。それは公平性、公正性、分かりやすさをねらってのことである。
確かに、成績や進学実績、あるいはクラブ活動の対外試合やコンクールでの成績は、「数字」として表すことも可能であろう。しかしそれらもまた「教育」全般においては、一部分なのである。人間の成長や発達、人間性の深化について、どれほど数量化が可能であるのか、それ以上に「途上(プロセス)」をどう把握するのかが、「評価」の最も重要な課題であると思われる。
しかし、パウロの語る「自己評価」は、殊、「信仰」や「教会」における「評価」なのである。「過大評価」せずに「慎み深く評価」すべき、と彼は言うのだが、それはその通りなのだが、そもそもどのようにしたら「信仰による評価」が正しくできるのだろうか。例えば「年間の礼拝出席回数」、「集会参加回数」、「献金額」、「勧誘者数」等を表にして書き出し、その結果を壁に貼って、一同に閲覧できるようにすることが、教会としての「評価」となるのだろうか。
自分を「過大評価する」とは、直訳すれば「大きく思う」、「優っていると見なす」という意味である。実際に教会でどういう具体的な問題が生じていたのか、詳細は分からないが、現代と同じく、初代教会も活動のほとんどすべては、教会員の奉仕によって成り立っていた。ここでは「預言」「奉仕(高齢者、子ども、食事等)」「教え」「勧め」「施し」「指導」等の役割分担が記されている。質的には異なるだろうが、現代の学校や福祉施設と同様な業務が、日々行われていたと思われる。
パウロはここで「体」のメタファーを用いて、「教会性」について理論を展開している。コリントの信徒への手紙には、さらに詳しく「教会=体」理論が展開されている。身体にさまざまな働きをする器官があり、それらがすべて有機的に結ばれて、ひとつも余計な働きをすることなく、つなぎ合わせられているように、5節「わたしたちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、わたしたちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形づくっており、各自は互いに部分なのです」と語るのである。おそらく教会員の間で、自らの働きの重要さを、他に対して殊更、誇示する向きがあったのだろう。いわば「奉仕自慢」である。
世の中には、「適材、適所」という価値観がある。ふさわしい資質の人材を、ふさわしい場所に配置する。さらには「潤滑油」のような要員も組織には必要であろう。これは利潤を上げ、目的を達成するのには、合理的な考え方である。ところが、教会は、「不適材、不適所」という考え方や、「素人主義(アマチュアリズム)」等、およそ不合理な論理が支配する場所なのである。確かに経営拡大や業績発展、利潤の追求という面からすれば、教会は非常におかしな世界である。
それはひとえに、教会の主、ナザレのイエスの生涯にその源があるからなのである。主イエスは神の独り子でありながら、この世に生まれ、しかもナザレの大工の子として育ち、人の子としてこの地上に生き、私たち人間のひとりとして生き、最期には十字架につかれて亡くなられたのである。教会は常に、この主の生涯に目を注ぎ、その主の後に従おうとするのである。主ご自身、その誕生の初めから終わりまで、「不適材不適所」を生きられたのである。わたしたちの誇りは、自分自身にではなく、この主にのみある。