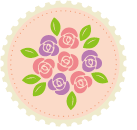 2006年に79歳で逝去された詩人の茨木のり子氏は、生前、自分が死んだ後に届けられる訃報を、届け先まで自らの手でしるし、家族の者たちに託したという。その文面は次の通りである。「このたび私 年 月 日(病名)にて/この世におさらばすることになりました。これは生前に書き置くものです。私の意志で、葬儀・お別れ会は何もいたしません。
2006年に79歳で逝去された詩人の茨木のり子氏は、生前、自分が死んだ後に届けられる訃報を、届け先まで自らの手でしるし、家族の者たちに託したという。その文面は次の通りである。「このたび私 年 月 日(病名)にて/この世におさらばすることになりました。これは生前に書き置くものです。私の意志で、葬儀・お別れ会は何もいたしません。
この家も当分の間、無人となりますゆえ、弔慰の品は/お花を含め、一切お送りくださいませんように。返送の無礼を重ねるだけと存じますので。
『あの人も逝ったか』と一瞬、たったの一瞬/思い出してくだされば、それで十分でございます。あなたさまから頂いた長年にわたるあたたかな/おつきあいは、見えざる宝石のように、私の胸に/しまわれ、光芒を放ち、私の人生をどれほど豊かに/して下さいましたことか・・・。深い感謝を捧げつつ、お別れの言葉に/代えさせて頂きます。ありがとうございました。年 月 日」
現在、「遺言」というと法的効力が取りざたされるので、「公正証書」の類として、きちんと署名捺印し、文面にしたものが求められる。「自分には財産などない」という人も、是非記しておきなさい、と勧められている。たとえわずかな財産でも、人間には物欲があり、それが人情と絡んで、いろいろいさかいの種となる。そして家族親族というごく近しい身内の関係では、なまじ親しいがゆえに争いもし烈なものになりかねない。現在は、遺言というと、自分の遺産、金銭や不動産の分与の事柄という色彩が強いが、この詩人の、自らの手になる「お別れの言葉」を読むと、「遺言」の本質、「言葉を遺す」ことの重さを知ることができるだろう。やはり詩人は、「言葉の人」である。何より言葉に生きて、言葉に死に、言葉を後に遺す者なのである。詩人にとっては、言葉しかない、ということがよく分かる。
茨木氏は、「感謝と思い出」と、それだけを「別れの言葉」としてお世話になった人々に伝えるのであるが、人間がその生涯を終えるときに、伝えることができる「最善」はこの二つしかないだろう。感謝もなく、良い思い出もない、これでは人間は何のために生まれて来たのか。生きる意味を端的に教えているようだ。「あなたさまから頂いた長年にわたるあたたかな/おつきあいは、見えざる宝石のように、私の胸に/しまわれ、光芒を放ち、私の人生をどれほど豊かに/して下さいましたことか」こう言えるものが人生にあるなら、それは何とかけがえのない宝であることか。
さて、創世記47章、ヨセフ物語の終幕である。ヤコブも高齢となり、目がかすみ、床から起き上がるのも困難な状態になっている。自分の父、イサクもかつてそのように老境を迎えたのと同じように。自分がまだ血気盛んな若者であった時、老いさらばえた実の父親を、目が良く見えないのをこれ幸いに、まんまと偽って、兄に授けるべき祝福を奪い取ったのである。今、ヤコブ自身も年老い、目がかすみ、父親のイサクと同じ立場になって、子どもたちに祝福を与える時を迎えたのである。人間というものは、自分が生涯に為したことは、時を隔てて、必ず自分自身に帰って来る、と考えている。だから「情けは人の為ならず」は、聖書の論理でもあると言えるだろう。
今日のテキストの後半に、ヨセフの二人の子ども達、つまり孫たちを祝福する場面が描かれる。ここでヤコブは不可解なふるまいを行う。二人の孫、長男マナセ、次男エフライムを、自分の養子としてとして位置づけ、さらに二人の頭に手を置いて祝福するのに、わざわざ手を交叉させて、祈るのである。古くは、これは十字架の予型だ、と見る学者もいたが、もった単純に、かつて自分が父イサクにしたこと、兄と偽って兄に下さるべき祝福を、弟がかすめ取ったのである。父を騙したことは、やはりヤコブの心の痛みとなっていたのだろう。やはり罪を背負ったままでは、人間は思い残すことなく安らかに死ぬことはできない。これがヤコブ流の筋の通し方だったのだろう。父親にしたことを、自分もまた引き受けて、その罪を改めて身に負おうとした、ヤコブ自身の了見の表れだろう。そんなことして今更何になる、というかもしれないが、人間は何であれ自分が納得できるけじめのつけ方をするものである。盗人にも三分の理というではないか。
ヤコブの遺言は、まず自らの葬りの場所について。エジプトではなく、カナンの地で葬られ、「先祖と共に眠りにつく」ことを願い求めた。「先祖と共に」という観念が、イスラエルの人々に強かったのは、「集合人格」的思考の産物である。「子孫繁栄、財産の増加、長寿」これらはイスラエルの人々が考えた「祝福」の具体化である。そしてそれらの幸いが向かう先は、「先祖と共に葬られる」ことなのである。祝福は、自分だけに訪れるものではなく、自分を通して、周囲の人間、さらに次の世代に広がって行く。だから聖書の人々は、自分さえよければ人のことなど構わない、というエゴイスティックな発想はしなかった。それでは「古代」という時代は生きられないのである。労働や生産、冠婚葬祭、あるいは喜びも悲しみもすべて「共に」という形を通して保たれた。個人的な幸せなど、ありえなかったのである。死後のこともまた同じように、神の祝福の中に生きた人間は、あの世でもひとりぼっちで捨て置かれるとは、考えられなかった。死んでからも人は「共に」なのである。ここで死と生を繋ぐものは、神の祝福である。神の祝福があって、人と人とは繋がれ、さらに生きている時も、死んだ後も、「祝福」が絆となるのである。だからヤコブの遺言も、自分の死と、子ども達の成長、繁栄への祈り、願いという形を取る。
ヤコブは死の直前で、ヨセフの子ども達と養子縁組を申し出る。これはエフライムに対する最大の敬意の表明である。やがてヤコブの12人の子ども達が、イスラエルの統一王国を形成し、北イスラエルはエフライムの一族の嗣業とされるが、ヨセフではなくその子エフライムが一族の祖とされたのは、ヨセフがエジプトで死に、エジプトに葬られたからである。養子縁組は、孫であっても子と同等という宣言であろう。エフライム族は、紀元前722年にアッシリアによって滅亡する。ヨセフの物語が文字に記された時は、その滅亡から大分時を経てからのことであろう。今は亡き、失われたエフライム一族の名誉を語り伝えるための伝承である。老人は、生と死の間にあって祝福を語り、その二つの間を繋ぐ者となる。いわば「生と死のコーディネータ」とも呼べるだろうか。