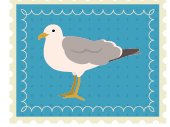
ある新聞紙面に、学生時代、課題で読まされた一冊の書物が取り上げられていたので、懐かしさもあって紹介したい。英国の歴史家E・H・カーは名著「歴史とは何か」(岩波新書)で「歴史上の未練を話題にして楽しむことはいつでも出来る」と皮肉っている。歴史にイフ(もしも)はないということか。毎夏この時期、やはりイフを考えたくなる。1945年、米英中の連合国が日本に無条件降伏を迫ったポツダム宣言を発表し、明日で76年。受諾は玉音放送前日の8月14日だった。直ちに降伏していれば、米国による原爆投下も中立条約を破棄してのソ連参戦もなかった。北方四島は奪われずに済んだかもしれぬ―。多くの日本人が思い浮かべる素朴なイフだろう。未練は膨らんでゆく。(7月25日付「卓上四季」)。
「未練を断ち切れ」、ひとりの優れた歴史家の警句である。未練の「練」は、「熟練」や「練達」の「練」で、ものごとに習熟していることを言うそうだ。「未練」は「未(いま)だ練れず」と読み下すように、本来は「未熟なこと」を意味する。1603年に刊行された日本語−ポルトガル語の辞典『日葡辞書』には、「Miren」は「臆病」の意とあり、「この語の本来の意味は、軽々しさ、軽薄さということであって、すぐに飛びかかったり、腹を立てたりするけれども、肝心の時になると、へまをしたり、気力をなくしたり、逃げ出したりするような人について言う語」と言う風に説明されている。一方、「あきらめきれないこと」の意味でも「未練」は、近世以前にすでに使われていたらしい。仏教で修業が未熟であることを「未練」と言っていたので、「俗世間をあきらめきれないこと」に結びついたのではないかと推測する。聖書諸文書の中で、もっとも早くに文字となった部分は、イスラエルの「歴史」を語る文書である。神はイスラエルの歴史において働かれ、歴史の中にそのみわざを現される。そこにイフや未練はないのである。
今日は使徒言行録から話をする。著者ルカに伝えるパウロの「遺言」とも言える言葉が連ねられている。著者はおそらく、使徒、パウロと宣教旅行の行程を共にした人だから、ずいぶん詳しくその次第を記している。この(いささか癖の強い)使徒と一緒に行動を共にしたというのは、それだけでもすごいと思うが、それだけこの人物の人格に興味津々だったのだろう。文学の題材あるいは、主人公、主要な登場人物は、円満な「いい人」では役足らずである。その当事者パウロが、今、懐かしい人々と今生の別れを告げて、出発とうとしている。その別れの場面を、歴史家のルカは見事に描き出している。
著者は主イエスのみ言葉の伝承を、さまざまな場所に自分から赴き、幅広く採集したのだろう。彼の書作だけに納められている、オリジナルのたとえ話や警句を沢山記している。今日の個所でも、福音書には出てこないが、恐らくは主イエスのみ言葉として、教会に親しく伝承されてきた言葉も引用されている。「受けるより与える方が幸いである」。この言葉は、初代教会の生活スローガンになっていたとも推測される。「恵み」というものの幸を教えている。「受けること」だけが「恵み」ではない。
「恵」という漢字は、元々、上部は「絹糸を巻いた糸巻き」のかたちを表し、下部はそのものずばり「心」を表しているそうである。「絹糸の糸巻き」とは高価なものの代表、特に女性にとっては、晴れ着を縫う時の必需品なので、思い入れの強い、特別に大切な品だっただろう。それを独り占めにしないで、周りの皆と分かち合う、大切なとっておきの着物、例えば婚礼、あるいは葬儀の着物を、皆で縫い合う、その心が「恵」という感じの成り立ちだと言われる。すると、「恵」という言葉には、やはり「与える方が幸い」という意味合いが込められていることになる。人間の生活の根本の感覚は、普遍、ユニバーサルであり、そういう心を今も大切にしたいと思う。当たり前に思える物を大切にする、それが失われようとする時こそが、一番の人間の危機なのである。日常とはそういうものである。
パウロの別離の言葉でも、強調されるのは、「恵」であり「言葉」である。パウロは言葉の人であった。今日の個所でも、「教える」「語る」「話す」「証する」という風に、「言葉」に関係する用語が沢山見出せる。しかしパウロにとってその「言葉」は、自分の言葉、つまり、自分の確信だとか主張とか、信念とかいったものではない。19節以下「涙を流しながら、また、試練に遭いながら、できるかぎりのこと、公衆の面前でも方々の家でも、あなたがたに伝え、また教えてきました。ユダヤ人にもギリシャ人にも」。
さまざまな状況の中で、そのほとんどは涙を流し、落胆し、疲れ果てている中で、そう、しか語ることができなかった「言葉」を語ってきた、というのである。つまり自分の中からあふれ出すように言葉が生まれて来て、饒舌に語ることができた、というのではない。自分自身は。空っぽであり空しい。言葉のたくわえなど何もない。そういう所で、その時その時に不思議に与えられた言葉があった、神からいただいたというしかない「与えられた、神からいただいた」言葉を語って来た、というのである。
それはまさに「恵みの言葉」と呼ぶしかないものであろう。恐らく私たちが、最後の最後まで失わないで、持ち続けることのできる唯一のものなのであろう。いつもの言葉を失っても、それが無くなっても、人と人とをつなぎとめるもう一つの別の言葉がある。その言葉を、現代人は、便利すぎる生活の中で失ってはいないか。
だからパウロはこう語る。32節「今、神とその恵みの言葉とにあなたがたをゆだねます。この言葉は、あなたがたを造り上げ、聖なる者とされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです」。ここで「ゆだねる」と訳されている用語の理解が、焦点である。よく「信仰とは委ねることだ」と言われる。神様にお任せをする、という意味合いであろう。しかし直訳すれば「あなたがたを神とそのみ言葉の、前に置く、据える,連れて行く」、ということである。ただ開き直って「神様、何とかしてください」ではない。その前があるだろう。人が、自分が、または誰かが、神の前、神の言葉の前に、行かなくては、何も始まらないだろう。そこから始まるものがある。そしてこれこそが伝道、宣教の最も根本の事柄であろう。教会に於いても、誰か人につながるなら、おそらく最後は絶望である。なぜならすべての人間の、この世の生活は、死で終わりになるから。それ以上に、人間こそが一番のつまずきの岩である。私たちがつながるものは、人を超え、死を超える、神とそのみ言葉だけである。
神学生の時、学部の恩師が語ってくれた体験を紹介する。その恩師がまだ神学生の頃、ご自分の先生が、重篤な病床にあったという。病院に見舞いに行くと、その大先生が、まだ神学生であった先生に、何か自分に慰めの言葉を語れ、という。「惧れ多い」としり込みすると、大先生は言う。聖書の勉強をしている者が、言葉を知らないわけがないだろう。君の愛する聖書のみ言葉を語りなさい、と言ったそうである。試練や苦難の中で、人間は自分の言葉を失う。しかしその中で与えられる「恵みの言葉」がある。曲がりなりにも、それをいただいている幸いを思う。
「神とその恵みの言葉にあなた方をゆだねる」、パウロの最期の祈りである。これはエフェソの長老たちに対する勧め、遺言と言うばかりでない。パウロ自身が、自分に向けて言い聞かせている節がある。私たちにとっても、同じではないか。最後はゆだねるのである。しかしわけのわからないものにゆだねるのではない。主イエスの前に、しかも十字架に釘付けられた主のみ前に自分を置き、そこで語られるみ言葉、神の言葉、聖書の言葉に私たちは自分を明け渡すのである。
沖縄の地方紙がこう綴っている。「メダルラッシュに沸き、新型コロナウイルスに恐怖を覚える。オリンピック賛美と怒りの声がやまず、国民の間に分断が走る。その中で私たちは広島、長崎の原爆投下から76年の日を迎える。原告全員への被爆者健康手帳交付を認めた「黒い雨」訴訟の高裁判決が確定した。2度の東京オリンピック開催で敗戦後の復興と国力を誇示したのに、被爆者救済は遅れた。そのことを重く受け止めたい」(8月5日付「金口木舌」。委ねるべきものを失い、未練の中に生きている私たちの日常がある。しかし、主はその只中に来られるのである。