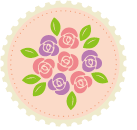
ことなく、一人の幸せが守られる、荒れ野のただ中に、そのような幸いを与えられるのであ三月を迎えた。この月の声を聞くと、実際の気温や気候にかかわらず、心なしか暖かな気持ちになって来る。西日本新聞にこうした記事が載っていた。
「日々の空模様は気になるのに、目線はいつも下向き。四季の移ろいを伝える木々や野鳥の姿にも目が向かない。そんな人が増えているようだ。気象衛星のおかげで予報の精度は向上した。外の景色には無頓着でも、天気は手元のスマートフォンが教えてくれる。その半面、人が体感で大気の変化などを察知する能力は退化していないか。大自然の営みはまだまだ科学では捉え切れないのに。
ウメ、ツバキ、タンポポ、ヒバリ、ウグイス、ツバメ…。全国の気象台は木々の開花や鳥の初鳴き、初見の日などを毎年チェックしている。生物季節観測と呼ばれる。気候が動植物に及ぼす影響や季節の進み具合を探る作業だ。福岡では1月にウメ、ツバキ、タンポポが開花し、昨日はヒバリの初鳴きが確認された。ただウメ、ツバキの開花日は昨年より遅かった。九州にはやっと冬らしい寒気が流れ込んだ。暖冬でも春はもう少し先なのか。動植物はそんな微妙な気象を察知しているのかも。人間の科学では正確な長期予報はまだ難しい」。
「生物季節観測」が今なお重要であるという。自然は微妙な気象を察知している。私たちはどうか。「空の鳥を見よ、野の花を見よ、注意して見よ」と教えられた主イエスの言葉がよみがえる。主はこうも言われた「あなたがたは、空模様は見分けることを知っているのに、時代のしるしは見ることができないのか」。
先週の水曜日は「灰の水曜日」であった。受難節の始まりである。カトリック教会では、この日のミサで、司祭が「灰」を指にとって、信徒の額に「十字のしるし」をつける儀式を行う。「灰」は旧約においては、「死」の象徴であり、これを身に被ることは「悲しみ、嘆き」の表現であった。しかし「灰」にはもう一つの意味がある。「灰」は強いアルカリ性を示すので、「灰汁(あく)」として「洗浄」に用いられたのである。だからここから「灰」は「悔い改め、方向転換」の象徴でもある。
主イエスは公生涯の直前に、荒れ野で40日の間「悪魔の誘惑」を享けられたと伝えられる。40日間にわたる受難節の折りに、この主の事績を想起することが教会の伝統とされてきた。「荒れ野」は「灰」のように「死」の世界である。そこで40日を過ごされ、悪魔と向かい合い、対決されたことは、「悪」からの方向転換(悔い改め)への道を開いてくださったことにも通じるであろう。
「荒れ野」とは、旧約では二重の意味を持つ場所である。人が居住せず、荒れ果てた場所のことである。人が住んでいないとは、そこで生活できないからである。そこは寂しい所で、野獣の住み処であり、悪霊はじめ魑魅魍魎が跋扈する処と信じられた。だから自分から好き好んで行く場所ではない。聖書の世界の荒れ野を旅してきた人が言うには、「激しい風の中に、何者かの声や、叫び、呻きが聴こえることがある」。
しかし他方、荒れ野は、イスラエルの人々が出エジプトの後に、40年もの間放浪した場所でもある。自分たちを奴隷から解放された神と、最も近くに歩んだ場所なのである。聖書の人々にとって、神との出会いの場所でもあった。だからそこで過ごした40年の間「着物も擦り切れず、足も腫れなかった」と想起されている。着物とは「守られる」、つまり必要が満たされること。足とは「生きる力」であり、希望や活力が失われなかったことの比喩表現である。
ここで記される「荒れ野」もまた、二重の意味がある。荒れ野は「悪魔」と出会う場所であり、同時に「天使が仕える」場所でもある。そしてそこにも主イエスがおられ、歩まれるのである。悪魔と天使と、さらに主イエスが同居している「荒れ野」、とは奇妙だが、非常に面白い風景ではないか。
新約の時代にイメージされている「悪魔」は、後世の神に反逆し、戦いを挑む強大な悪の勢力という感覚はない。何事かの悪事を為すというよりは、もっとしたたかに、人間のまとわりついて、巧妙に道を踏み違えさせるという、隠微な存在である。今日のテキストでの「悪魔」もそのような姿で記される。この世の中には、罰せられないけれど、ひどく人間を貶め、生命を損なうような事柄が確かに存在する。「見て見ぬふり」「記憶にない」「知らなかった」「想定外であった」等々、悪はしたたかである。
「石がパンになるように」「天使が支える」「すべてを与えよう」、これらの悪魔の言葉は、そのまま罪に問える言辞ではない。余程、国会のヤジの方が下品である。そして石がパンになり、天使がすべての危機から人を守り、貧しさがこの世から払しょくされることは、ある意味では理想の社会の到来ということもできるだろう。干ばつが飢餓を起こし、紛争や災害によって子どもたちが殺害され、貧しさゆえにテロに駆り立てられていく。この3つは密接につながって、この世界を暗澹たるものにしている。まさに悪魔の言葉は、この世のリアルな現実を私たちに突きつけている。
悪魔の語る「飢餓」「危機」「貧しさ」からの解放は、古代のみならず現代の世界の課題とも言える。これにどう向かい合うかで、人間のほんとうが露わにされるのである。最初からこうした無理難題に対しては「解決は無理なんだい」、とあきらめるか、「革命によって」「力によって」とばかり人々を鼓舞するか、あるいは、「責任者出てこい」と誰かを悪者にしてその罪を糾弾するか。
主イエスはどうされたか。悪魔に対しての最後の言葉は、「あなたの神である主を拝み、主に仕えよ」。あなたの神を拝み、それに仕えよ、というのである。ならば、神はどこにおられるのか。あなたの神はどこにおられるか。神は神殿の中にいますのか。王宮の中に、大伽藍の中に鎮座ましますのか。そうではないだろう。人が、世界が今、「飢餓」「危機」「貧しさ」を抱えて苦しむのなら、神がおられるのは、そこ以外にはないのではないか。主イエスは、霊によって荒れ野に行かれたと言われる。聖霊は人を神へと導く働きをする。神の居ます所がどこかを教え、そこに私たちを招くのである。そこに悪魔が居ようとも、「飢餓」「危機」「貧しさ」の中に、それらと共に神はいます。だから神の子主イエスは、この世に来られ、飢えた人、病や暴力に傷つけられた人、貧しい人の下に自ら行かれ、働かれたのである。そこに神がおられるから、その神を拝み、ただその神に仕えるためである。
ある沖縄出身の一人の女性、大学非常勤講師の門野里栄子氏が、自分の生い立ち、そして現在をこのように語っている。「みんなが幸せでいられる社会のために」というと、抽象的な言葉に聞こえるかもしれない。しかし、亡くなった母親が残した言葉として心に留めている娘にとっては、具体的な生きた言葉である。
母親は、75年前の沖縄戦で自分の父親と長兄を亡くした。一家を養い、きょうだいを学校に行かせるために、自らが子守奉公に出て働き手となった。学問に触れる機会もなく、字も読めないまま嫁いだ。そんな母親が、のちに「日本母親大会」で何百人もの聴衆を前にして、米軍との土地闘争の現状を訴えた。
女性差別は恐ろしい。同時に2人の命を奪っていたかもしれない。跡継ぎの男児を強く期待される中で、2人の娘を産み、3人目を身ごもった母親は「もし女の子だったら、この子を殺して自分も死のう」と思い詰めていた。離れ小屋でひっそりと出産した赤ん坊は、上の子どもたち以上に大きな産声を上げた。それを聞いて、生きていく覚悟を決めた。その娘がのちに、家族の窮状を救い、ゆるぎない平和活動者となる。
娘はずっと、平和活動を「すごい母」任せにしてきた。親から米軍への抗議行動に誘われてもついて行かなかったし、土地闘争をしている家の子と思われるのも嫌だった。ところが突然、母親を事故で失う。ポッカリ空いた欠落は、自分がやるべきことだったと気づき、母から残された大きな課題だと受け止める。
「やっぱり自分も学びたかった」とつぶやいた母親は、戦争や女性差別の苦難の中で、懸命に生きてきた。母親の闘う姿は、平和活動を体現している。宿った命が選別されることなく生を受け、爆音のない静かな環境で育ち、誰も傷つけず誰からも傷つけられないような世の中。一人の幸せが守られる社会こそが、「みんなが幸せでいられる社会」である。
「娘はずっと、平和活動を『すごい母』任せにしてきた。親から米軍への抗議行動に誘われてもついて行かなかったし、土地闘争をしている家の子と思われるのも嫌だった」、その娘が母親の立つ場所、戦った場所に、いつしか連れ戻されるのである。主を荒れ野に導いた「霊」は、今も私たちを神の居ます所、語られる場所に私たちを導く。そこは荒れ野である。悪があり、悪の試みのある場所である。しかしそこにこそ神はいまし、わたしたちに幸いを与えるのである。命が選別されず、暴力に支配される。