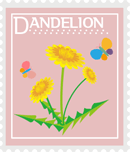
小さい頃読んだ(見た?)、「岩波の子どもの本」シリーズの中の一冊に、『ツバメの歌・』ロバの旅』という題名の絵本があった。今でも出版されているかもしれない。この絵本は、2つの別の物語が合本されているという体裁で、異なる話が並べられており、どうつながっているのかが不思議で、子ども心に困惑した思い出がある。特に『ロバの旅』は、南米エクアドルが舞台で、絵から発せられるラテンの雰囲気にも、「未知の世界」という強い印象を受けた。まだバナナが高価で、あまり口にできない時代に、回り中、一面バナナの木の中での生活に、何となくあこがれを抱いたりもした。しかし、主人公の子どものロバが、母親と別れ、たったひとりで、何かを求めて旅をする、というストーリーに、寂しさや不安、違和感と共に、幼いながらも漠然と「人生」というものを考えさせられたように思う。
物語で、この子ロバは、耳を振って耳のさした方に何日も進んで行く。旅の中で見るものすべて、初めてのことばかり、舟にも乗って、宿なしロバの当てのない旅が続く。ココアの豆がたくさん干してあるチョコレートの町、金山のそばの砂金の町にも滞在し働くが何かを求める旅は終わらない。「何かさがしているロバくん、こんにちは、何か見つかったかね」こんな風に声をかけられながら。
この絵本の印象がよほど強かったのか、福音書の描く「エルサレム入城」の物語を読むと、必ず絵本に登場したあのロバのことを思い出す。主イエスがエルサレムに入られる時の様子は、4つの福音書すべてに記されている。その記述の長短や強調点は異なっていても、「ロバ」に乗って入られたことを告げているのである。
旧約の預言者は、やがて来るべきメシア(救い主)をこのように預言した。「娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ 歓呼の声をあげよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者/高ぶることなく、ろばに乗って来る/雌ろばの子であるろばに乗って。わたしはエフライムから戦車を/エルサレムから軍馬を絶つ。戦いの弓は絶たれ/諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ/大河から地の果てにまで及ぶ」(ゼカリヤ書9章9~10節)。
「馬は王の乗り物」であり、「ロバは民衆の乗り物」である。颯爽と馬にまたがる姿は、王たる者の威厳を、否が応でも高めるであろう。ところがこの預言者によれば、イスラエルのメシアは、「馬ではなくロバに乗る」と告知される。それは、神がすべての戦車と軍馬を絶ち、戦弓を折り、すべての民に「平和」を告げられるからである、という。その象徴こそが、「ロバに乗るメシア」である。この預言者のヴィジョンは、聖書の歴史を生きて来た人々にとって、自らの経験に裏打ちされた、「祈り」から生まれてきたものであったろう。それ程、イスラエルの人々は、戦争に脅かされ、戦いに明け暮れる歴史を味わって来たのである。王が馬ではなく、ロバに乗る日こそ、私たちにとって、最も望むべき平和の成就なのだと。
この預言は、聖書の人々にとって、強く心に刻まれていたことだろう。主イエスもまた、この預言の言葉を、よく知っておられたから、エルサレムの城内に入ろうとする時に、このゼカリヤの言葉に従ったのであろう、しかも十字架を予期する中で。
福音書すべてに記されている記事だとは言え、それぞれの書き方を比較しながら、丹念に読めば、描写の違い、即ち、それぞれの福音書記者の独自な視点が息づいていることを、見出すことができる。どうやらマルコは、「ロバ一般」ではなく「この子ロバ」という具体的なひとりに、関心を向けているようなのである。子ロバを連れて来るにあたってこう指示されている。「向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだだれも乗ったことのない子ろばのつないであるのが見つかる。それをほどいて、連れて来なさい」。マルコの描き方は詳細にわたっている。「向こうの村、入るとすぐ」、聞く人がまるで目に見えるように語るのである。しかしそれにもまして「まだ誰も乗ったことのない子ろば」という表現を、どう理解するだろうか。この文言は、不思議なことにマルコしか記していない。
家畜を宗教的な、いわゆる「聖なる目的」に用いる場合、律法では「人の未だ乗ったことない」あるいは「農耕に供したことのない」家畜を用いることが規定されている(民数記19:2。申命記21:3)。但しその家畜とは、「雌牛」であって「ロバ」ではない。丁度、結婚式の時に新郎新婦の乗る車、あるいは葬儀の際の霊きゅう車は、専用車両を用いる、といった感覚である。古代の家畜は、現代の自動車のようなものだから、メシアをお連れする「家畜」もまた、「新車」でなければ失礼にあたる、と福音書記者は考えた、というのも頷ける。
但し、「まだ誰も乗ったことのない子ろば」という表現には、宗教性ではなく、「未熟」あるいは「貧弱」という意識が込められているのではないか。まだ成長途上か、生まれつきの個性なのか、ひ弱で、力弱く、小さな躯体だから、十分な働きに耐えられない、そんな小さなロバ、というようなニュアンスで、福音書の著者は記しているのではないか。
私たちは、人間の能力という時に、個人単位の、一人の人間の持っている力をイメージする。他と比べてここが優る、この点が劣る、それを数値化して客観的な装いによって、目に見えるもの、証拠(エビデンス)とするのである。学校教育においては、一人ひとりの子どもが、それぞれ百点を目指して努力し、走るように求められる。百点取るのは大変だが、それでもゴールは定められているのである。やり方次第で何とかなるかもしれない。
ところが人生の歩みでは、百点がゴールではない。到達点は絶えず先延ばしにされるのである。四百点も五百点も求められる場所で、自分一人で頑張ろうとするなら、おそらく命がもたないであろう。だから、「一人で」ではなく「皆で」という働きが、必要になって来るのである。誰と共にあるか、誰と共に歩んでいるか、は、ひとりの弱さ、貧弱さを超えて行く力となるであろう。
最初に紹介した絵本だが、旅に出た子ロバは、最後にひとりの子どもと出会い、その子と共に生きようと決意する。そして言うのである「『だれかのロバになること』を探していたんだ」。そのような「誰か」とは、まさしく「エル・ニーニョ(神の子)」なのである。