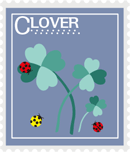
私が社会人になった年、1983年にひとつの映画が公開された。『家族ゲーム』、森田芳光監督、松田優作主演で、お二人とも既に鬼籍に入られている。成績の悪い次男は高校受験を迎えている。新しく雇われた家庭教師(松田優作)によって引き起こされる騒動をコミカルに描いている。子どもが何に興味を持っているのか知ろうともせず、学歴に異様に固執する父。母はそんな夫に逆らえない。両親や弟との間に一線を引く冷めた兄…。
この映画に印象的な風景が映し出される。細長いテーブルに向かって夫婦と息子2人の家族4人が、横一列に並んで食事している。肩がぶつかり、何とも窮屈で食べにくそうだ。
どんなに幸せそうに見える家庭にも、どこかに不協和音は流れてはいるだろう。家族もまた人間の集まりだからである。風変わりな食卓のシーンは、お互いの心に向き合おうとしない家族の姿の象徴だろうか。そしてそういう家族の時代の始まりを、この映画は切り取っているのだろう。
横一列の食事風景と言えば、思い出されるのは、レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』である。あまりに有名な作品なので、そういうものだという思い込みで、違和感を感じないのだろうが、主イエスと12人の弟子たちが、横並びで食事をしている。十字架に付けられる前の晩に、弟子たちと食した過ぎ越しの食事、「最後の晩餐」は、まさかこんな有様であったはずはない。この有名な絵は、もともと修道院の食堂の壁に描かれた絵画なのである。たくさんの修道僧がこの絵を取り囲んで、毎日の食事の時を過ごす。主イエスの大いなる恵みは、十二使徒ばかりでなく、そのみ前にあるすべての人々のところへ、とのメッセージを伝えるものであろう。
違和感を抱かせる横一列の食事。まさかそれが奨励される世の中になろうとは思いもしなかった。新型コロナウイルス感染の長期化に備え、国の専門家会議が「新しい生活様式」を提言した。具体例に「食事は対面ではなく横並びで」とある。ほかにも「人との間隔は2メートル」「食事中はおしゃべりを控えて」「誰とどこで会ったかをメモを」等など。事細かな決まりごとを暮らしの中に取り入れるのは、正直大変だろう。それはコロナ禍を乗り越えることの難しさの裏返しでもある。果たして私たちはこれを実行できるのか。そしていつまで続けなければならないのか。
今日の聖書個所は、ローマ書の中でも、良く知られ読者に共感を呼び起こすテキストで。ある。15節「わたしは自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです」。確かにこの言葉は身につまされる。誰もどこか心当たりがあるのではないか。何が大切で、何が重要か、程度によりけりであろうが、私たちには分かっているところがある。今、何をすべきなのか、何をしてはいけないのか。まだもの心もつかない赤子ではないのだから。ところが分かっているのに、実行できない。今はこれをやるべきではない、やってはならないのに、「分かっちゃいるけど、やめられない」のである。
先ほどの「新しい生活様式」であるが、ある芸能人が、「どのくらいの期間、実行すれば良いのですか」と尋ねたところ、専門家が「1年とか2年とか今の段階では言えない、最低でも4年は続ける」との答えに、その芸能人は絶句していた。数か月ならば「新しい生活様式」を努力して実行する気持ちにもなるだろう。しかし、こうした生活が延々と続くとなると、どうだろうか。
ある仏教のお坊さんはこう語る。「お経を唱える以外は、口を利くことは許されません。食事は楽しみではなく、修行そのものです。気になるのは横並びの食事風景です。修行時代の辛さを思い出すから言うわけではありませんが、あれほど寒々しい光景はありません。何が面白くて、黙々と食べ物を口に運んでいるんだ、という雰囲気です。あくまでも非日常の世界を生き抜くための暫定措置であると思ってください」。厳しい修行を経験したお坊さんも、この「新生活様式」は「生き抜くための暫定措置」と評するのである。
パウロの場合、これらの「望むことを実行せず、憎むことを行う」という嘆きは、「律法」を巡って沸き起こっている事柄なのである。旧約には「律法」と呼ばれる神の誡めが、全部で613あると言われる。それらの戒律のうち、248は ミツヴォット・アセー(「積極的戒律」行動を促す命令)、365は ミツヴォット・ロー・タアセー(「消極的戒律」行動を慎む命令)である。365は一年の日数に対応し、248は古代ヘブライ人が人体の骨と重要な器官の数であると信じられた。即ち一年365日、律法に則って「生活様式」が組まれているというのが、ユダヤ教であり、しかもそれは生きている限り、一生の間、続くのである。パウロでなくても、「望むことは行わず、憎むことを行う」と言いたくもなるではないか。そしてそれは「永遠の生命」にかかわる事柄なのである。
なぜできないのか。その理由をパウロはこう述べている。20節「もし、わたしが望まないことをしているとすれば、それをしているのは、もはやわたしではなく、わたしの中に住んでいる罪なのです」。他人は「努力が足りない、根性がない、心が弱い」といろいろと勝手に論評するであろう。そうかもしれない。しかし、正直言ってできないのは、何か自分の内に邪魔する存在があって、それがいろいろとちょっかいをかけて来る。だから、なぜか撃ち負けてしまうのだ、とパウロは言う。24節「わたしは何と惨めな人間なのでしょう」。この惨めさを心底味わう時に、私たちはようやくキリストのところに赴けるのではないか。自分の力で何でもできると信じていた。自分の努力次第で何とでもなると考えていた。しかし「今は」。
「石鹸で流れないもの、それは恐怖心」というキャッチがある。日本赤十字社がアニメ「ウイルスの次にやってくるもの」で呼び掛けている。先が見えない、見通しが効かない、いつまで続くのか分からない時に、人は無力感を抱き、疲れ、怒り、虚無感に陥る。「何と惨めな人間だろうか」というパウロの告白は、私たちの言葉でもある。だからこそ、そこから十字架の主を。本当に見上げることができるのではないか。「エリエリレマサバクタニ」から何が起こったのか、本当に知ることができるのではないか。