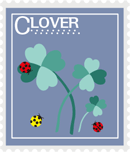
列王記は、ダビデからソロモンへの王位継承に始まり、イスラエル・ユダの滅亡までを語る歴史書である。ソロモンの栄華と呼ばれる繁栄と豊かさの極みにあって、すでにイスラエル統一王国にほころびが見え始め、国の分裂、北王国の滅亡、次いで南王国の滅亡とバビロン捕囚が語られる。その間、400年にわたる歴史が綴られている。
国の滅亡という一大事は、突然、訳もなく生じるものではないだろう。ポンペイのような天変地異の大災害であっても、滅亡に至るにはそれなりの理由がある。イスラエル王国も同様に、歴史家は自分たちの国の滅亡の理由を、自らの長い歴史の歩みを丹念にたどることによって、詳らかにしようとしているのである。
では、その理由とは何か。最も大きな答えは、イスラエルが「らしさ」を失ってしまったから、と言い表すことができるだろう。「国民的ジョーク」なるものがある。「イギリス人は考えながら歩く。ドイツ人は考えてから歩き出す。イタリア人は走った後に考える。何も考えずに走っているのがアメリカ人なら、それを見て自分も走り出すのが、日本人である」。国民性をそんなに単純にステレオタイプ化はできないだろうが、何となくそういう「らしさ」、いわば「傾向」があるように思われる。
イスラエルの一番の「らしさ」は、彼らの神「ヤーウェ」である。彼らは自らを「神の民」、ヤーウェから選ばれた民と意識したのである。その神との関わりの中で、イスラエルは自らの歴史を歩み、生活を営んで来た。ヤーウェなしには、夜も昼も明けないのである。そういう所から、独特の観念や価値観が形成されてきたのである。今日の聖書個所には、アハブ王の姿を通して、その具体的な事例が伝えられている。
イスラエルの王アハブ。北イスラエルの王として22年の間在位(前871~852年)、シリアの王女イゼベルを妻に迎え同盟を強化した。イゼベルはシリアのバアル崇拝をイスラエルに導入したが、これは近隣諸国の文化の移入であり、またイスラエルの宗教状況の国際化ともいえる。そして、シリア人やカナン人、フェニキア人との交流や同盟を通じて経済力と軍事力を増大させ、婚姻によりユダに影響力を行使し、ダマスコに並ぶ北パレスチナの地域大国としてイスラエルの地位を飛躍的に高めたとされる。
在任中、政治外交的にアハブは、有能な王としてふるまったようだ。しかし国際的に開かれた国家が担う宿命として、外国の文化や価値観に強く影響を受け、イスラエル固有の伝統が揺るがされることにもなった。それゆえ、イスラエルの伝統の破壊者として、アハブはエリヤを始めとする預言者から、鋭く批判されるのである。
今日の個所では、アハブの宮殿に隣接する土地、ナボト所有の、猫の額ほどのぶどう畑の土地を巡って生じた、残忍な事件のことが伝えられている。アハブはこの土地がえらく気に入り、ナボトに売買を持ちかける。しかしナボトはきっぱりとその申し出を断る。相手は時の王である。それでも譲れないことがある、イスラエルのひとつの「らしさ」である。なぜだめなのか。3節「先祖から伝わる嗣業の土地を譲ることなど、主にかけてわたしにはできません」。この返答に王は機嫌を損ね、腹を立てて宮殿に戻った。そればかりか、寝台に横になって、拗ねて顔を背け、飯も食わなかった、というのである。これではまるで反抗期の子どものようである。確かにアハブは父王オムリの王子であり、毛色のいいボンボンである。人柄という事もあろうが、それ以上に、このやり取りの行には、イスラエルの土地に対する独特の価値観が、背後に潜んでいると言えるだろう。
イスラエルの民は、もともと自分の土地を持たない、流浪の民、放浪の民族であった。出エジプトの後、40年にわたる荒れ野での放浪生活の後、神ヤーウェによって、約束の地「乳と蜜の流れる地」、カナン(パレスチナ)に自らの土地を得、ついに王国を築くに至ったのである。こうした歩みを辿ったイスラエル人の、土地に対する感覚をよく伝える物語が、創世記、アブラハム物語の中に収められている。
創世記23章に、カナンのキルヤト・アルバで、アブラハムは最愛の妻、サラを失う。亡妻を葬るために、アブラハムはその地の住人ヘト人に土地の購入を願い出る。4節「わたしは、あなたがたのところに、一時滞在する寄留者ですが、あなたがたが所有する墓地を譲ってくださいませんか。亡くなった妻を葬ってやりたいのです」。ヘト人たちは彼に同情して、ただで提供することを申し出るが、アブラハムは断固としてそのありがたい申し出を辞退し、対価を支払い購入するのである。これがイスラエルが初めてパレスチナに土地を所有した経緯である。
なぜアブラハムは殊更に代金を払おうとしたのだろうか。「只より高い物はない」、ことをアブラハムは知っているのである。つまり、きちんとした明朗な取引なくしては、後々いろいろ面倒が生じるからである。特に「寄留者」相手の取引となれば、猶更である。この物語は、イスラエルがどのようにパレスチナで、自分たちの土地を得て、そこに暮らすことができるようになったかを、たとえ話のように伝える物語であろう。
例え、猫の額のような土地であっても、「嗣業の地」、つまり自分の父祖たちが、アブラハムのような血のにじむ思いをして獲得した、曰くの土地を受け継いでいるのである。そしてその土地は本来、神のものであって、それをお借りしているに過ぎない。そういった土地に対する観念を、ナボトははっきり持っているし、アハブもまたそのような感覚を持っているのである。だからナボトから拒絶された時、大きな不機嫌に陥ったと言えるだろう。イスラエルの伝統という壁に、この王は直面したのである。
しかしシリア生まれの妻、イゼベルは違った。イスラエルの「らしさ」を知らない人間なのである。土地など自由に売買して当然、投機の対象であり、単に右から左に動かす物でしかない。そんな土地に拘るイスラエル人を嘲笑い、残忍な計略を立ててナボトを謀殺し、まんまとご執心の土地を手に入れる。現代の不動産投機を見るような雰囲気である。イスラエルの「らしさ」が、失われて行く様が、物語として鮮やかに語られる。こうしてイスラエルは滅亡へと足を踏み入れてゆくのであると。
しかし、アハブもまたひとりのイスラエル人なのである。預言者の言葉によって、己の罪の深さを知り、「衣を裂き、粗布をまとい、断食して」悔いたという。この残酷な物語の中での、せめてもの慰めであろうか。