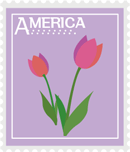
列王記は、イスラエルとユダの王の事績と共に、エリヤ、エリシャといった「前の預言者」、(イザヤからマラキまでの「記述預言者」の先駆者として)の活動を記していることに特徴がある。この二人の預言者は、師と弟子の関係で、エリシャはエリヤの後継者となった預言者である。
エリヤ、エリシャたち、前の預言者は、王宮に出入りし、王家と密接な繋がりを持っていたようである。異教の導入に積極的だったアハブ王は、エリヤとの強い確執が伝えられているが、「わたしの敵よ,わたしを見つけたか」と王がいまいましげに預言者を呼ぶ箇所が、特に興味深い(列王上21章20節)。この二人、余程そりが合わないのである。当時の預言者は、権力を誇る王に対しても、大胆に恐れることなく神の言葉を語ったのである。
ところがその一方で、アハブの王妃であるイゼベルに対しては、エリヤは「(気力が失せ)、恐れて逃げ出した(列王上19章3節)」と伝えられる。さしもの預言者も人の子である。特にユダ王国よりも、北のエフライム王国において、王家と預言者の関係が密であることは、神殿のおひざ元のエルサレムでは、その政治形態が、早くから神殿体制を基盤にして形成されたからであると考えられる。
後の「記述預言者」達と異なり、エリヤ・エリシャら前の預言者たちは、様々な奇跡を行う異能者であり、英雄伝説的な要素を物語の内に多分に含むので、民間伝承に根ざした文学として成立したのであろう。今日の聖書個所には、エリシャによる二つの奇跡の物語が記されている。そのどちらも、当時の生活の実際を生き生きと映し出しているだろう。市井の人々が、その日常生活において何に悩み、どのような困難を抱え、どう行動したのか。そしてそれらの当たり前の人々の生活に、神がどのように関わってくださるのか、素朴で飾り気のない文章で、巧みに語られている。これらの奇跡は、エリヤの物語にも、似たような内容の話が記されている。つまり庶民がこの時代の預言者に対しての、どんなイメージを抱いていたのか、どんなかかわり方をしていたのか、このような物語を通して、知ることができるであろう。
最初は、「オリーブ油の奇跡」である。聖書では他の個所でも、ただ「油」と記されるが、これは「石油」でも「てんぷら油」でも、「ごま油」でもなく、「オリーブ油」であることに間違いはない。それ程上から下まで、生活に密着、欠くべからざる物品が、「オリーブ油」なのである。
オリーブの歴史は古く、紀元前3000年には地中海沿岸で栽培が始まっていたとされる。現在も生産国の98%以上は地中海地域に集中している。日本では1910年頃、香川県の小豆島で初めて栽培に成功したという。オリーブから採取される油(オリーブオイル)の用途は多岐にわたる。聖書にも至る所にその記述が見られるように「儀式用、食用、薬用、灯火用、化粧用」と、歴史を超えて、ありとあらゆる場面で、地中海世界周辺の人々の生活を支えてきた。現代でも、コレステロールの軽減、動脈硬化、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などの予防、糖尿病の改善、便秘解消に加え、老化防止や美容、日焼け止めにも効果を発揮する等、食品の優等生のようにも受け取られている。それにまつわる物語である。
エリシャの親しい知人の奥方が、苦境に立っている。旦那が亡くなり、その債務によって、債権者により子ども二人が奴隷に売られる、という不運である。古代で、聖書の世界でも最も弱い立場に置かれたのは、妻と子どもである。どのような生活でも、後ろ盾がいるからこそ成り立つ社会の仕組みであった。未亡人とその子ども(年若く、まだ十分に就業できないくらいの年齢)は、一番の後ろ盾を失った状態に置かれるのである。
初代教会にも「やもめ」(とおそらく捨てられた「子どもたち」)が数多くいたことが伝えられているが、それは教会が最も弱い立場に置かれた人々に、しっかり心を向けていた証拠である。それが主イエスの愛のわざを、自らも受け継ぐ働きと考えたからである。そしてその原点は、エリヤやエリシャ物語の、苦境に陥った「やもめ」についての物語に遡るものであるだろう。
エリシャの奇跡によって、油壷からオリーブ油があふれ出し、それを売って生活の資を得たという話は、ただ経済的な苦境が解消されたという金銭の事柄のみならず、この未亡人と幼い子どもたちの生活に、「喜び」が回復されたことを告げるものであるだろう。夫、父親が亡くなり、灯が消えたような生活に、再び「灯」が点されたことが、暗に語られている。旧約では「オリーブ油」は「喜びの油」とも言い換えられているのである。
それに続く話は、前の物語とは打って変わって、シュネムの富裕な家の、これまた奥方についてである。通りがかりの預言者のために、毎度、食事を提供していた裕福な夫人が、エリシャのために自宅に宿泊場所をも作り、もてなしたというのである。イスラエルには古代から行きずりの預言者や宗教者を宿泊させ、もてなす伝統があったことが分かる。主イエスは弟子たちに巡回宣教を命じているが、そういう行きずりの者をもてなし、その話に耳を傾ける習慣は、「敬虔さ」ばかりでなく、旅をすることで広く見聞を培ってきた者の話を家族始め、一族郎党、近所の者たち、皆で聞くことは、大きな楽しみであったことは確かであろう。主イエスの言葉も、そのようにしてヘレニズム世界に広まって行った。
裕福だから、暮らしに事欠くことはないとはいえ、生きる悩みが何もないわけではない。この奥方には、子どもがいなかったのである。もうすでに夫は大分、年老いていたようだ。それをエリシャに告げる者があった。エリシャは来年に、子どもの誕生を予言する。この物語は、かのアブラハムとサラの物語を下敷きにしていることに、間違いはなかろう。天使によって告げられたイサクの誕生、それは「イサク(彼笑う)」という名前の意味に込められているように、「喜び」の誕生であった。あの貧しいやもめの生活にも、「喜び」がもたらされ、このシュネムの金持ちの女にも、「喜び」がもたらされた。人が何によって生きるのか、まったく違った境遇でありながら、同じことが問われている。
この2つの物語でとりわけ興味深いのは、預言者エリシャが、この二人の女性にまったく同じことを語っていることである。2節「何をしてあげられるだろうか」、そして13節「あなたのために何をしてあげればよいのだろうか」。この預言者の生きる姿勢が、明確に記されているだろう。上から見下げるように、命令し叱責し、裁くのが預言者ではない。「あなたのために、何ができるだろうか」。そしてこの言葉は、主イエスの言葉でもある。「何をしてほしいのか」、主イエスは出会った人々に、そのように問うたではないか。だから私たちも、ありのままに主に求めることができるのである。それは神のみこころでもある。