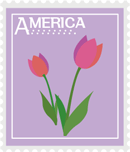
祝イースター、礼拝堂に共に集い、喜びの礼拝を守れることを、深く感謝したい。
さて、ある大手旅行会社が、イースターにちなんで、「卵」が有名な旅行先をめぐる「イースターエッグハント旅」を提案し、その旅におすすめの国内旅行先とホテルを発表している。例えば「箱根強羅温泉、大涌谷で『黒たまご』を賞味しましょう」、また「信州、野沢温泉で、『温泉卵』を作る体験をしましょう」。あるいは「大分、別府で、『とろける地獄蒸しプリン』を味わいましょう」という具合である。
この国の人々の生活に、クリスマスは確かにイベントとしてではあるが、既に根付いていると言える。イースターも何とか、そうできないか、コロナ禍で冷凍庫の中のように冷え込んだインバウンドを、何とか回復させたいとの業界の思惑が滲む。だから熱く湯気の立つ「温泉卵」という訳ではなかろうが。それにしても、思想でも慣習でも、他からもたらされた何某かのものが、全く異なる文化に根付く、というのは、いったいどういう状態になることであろうか。
ある新聞に、英絵本作家のデビッド・マッキー氏の訃報(87才)と共に、彼の代表作『せかいでいちばんつよい国』が紹介されていた。「昔、とても大きく強い国があり、その国は自分たちの暮らしが最高だと信じていた。そこで、その国の大統領は、世界中の国を征服すれば、それらの国もすべて自分たちと同じように暮らせるのだから、幸せになると考え、戦争をして片っ端からいろいろな国を征服した。そして、ついには征服されていない国は1つになった。その国はあまりに小さな国だったから、大統領も放っておいたのだが、ひとつだけ征服せずに残しておくのも気持ちの悪いものだと、完全征服のため兵隊たちを伴って戦争に出かけた。
ところが、その小さな国には兵隊はおらず、平和そのもので、大変のどかだった。戦争に来たはずの大統領や兵隊たちは『お客様』のように扱われ、食べたこともないような美味しい食べ物を食べたり、歌を教わったり、珍しい石けりの遊びなどを教わった。あまりに平和で、兵隊たちはその小さな国にすっかり溶け込んでしまう。これではいかん!と激怒した大統領は、小さな国で生活になじんでしまった兵隊たちを送り返し、新たにしゃきっとした兵隊たちを呼び寄せた。ところが、それらの兵隊たちも時間の経過とともに、同じように小さな国に溶け込んでしまった。大統領はたくさんの兵隊は不要と判断し、数人の見張りとしての兵隊を残して国に帰ることにした。見張りとしてきたはずの兵隊たちもやはり小さな国に溶け込み、住人たちと同じように畑を耕したりして働いた。
住民の大歓声に迎えられて帰国した大統領は、いつの間にか自国にあの小さな国の文化が浸透していることに驚いた。しかし、そうした文化もすべて戦争によってぶんどってきたものだからと解釈した。ある晩、自分の子どもから歌を歌って…とせがまれた大統領の口から歌われた歌は、すべてあの小さな国に滞在していた時に教わった歌だった」。原題は『THE CONQUERORS』(征服者たち)。本当に「征服」したのは、どちらなのか。紀元313年に、ローマ皇帝コンスタンティヌスが語ったとされる言葉、「お前の勝ちだ、ナザレ人よ」が思い起こされる。
今日の聖書個所は、マルコ福音書の掉尾を飾る復活の物語である。元々の福音書では、8節で終結していたらしい。突然、物語がぷつんと途切れる、という感じである。しかしこれもこの著者の深い意図から出ているのだろう。「あの方は、ガリラヤへ行かれる」という象徴的、隠喩的な言辞をもって、福音書は閉じられるのであるから。「ガリラヤ」とはどこなのか、単に地理上の位置を示すものではない。そこに行ったならば、あの懐かしい主イエスに、再びお目に罹れるのである。その場所とはどこか。
先を急ぎ過ぎた。十字架から3日目、日曜日のごく朝早くに、マグダラのマリアら、女たち三人が、主イエスの遺体を納めた墓へと出かけていったという。十字架で息を引き取られ、安息日が始まる夕刻が迫っていたので、あわてて主イエスの身体を取り下ろし、墓に葬ったのである。愛する故人のため、何も敬弔のまことを尽くせなかった。せめてその身体に直に手をふれて、香料を塗り、しばし別れの時を過ごしたい、という情愛あふれる心で、女たちは墓に急いでいる。ところが、人間の生きる営みには、いつでもどこでも「心配の種」は潜んでいるもので、「だれが墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうか」と話し合っていたという。ユダヤの墓は、死人が外に出てうろつかないようにと、入り口を重く大きい石で塞ぐのである。
ところが「目を上げて見ると、石は既にわきへ転がしてあった」というのである。彼女たちの心配は、まったくの取り越し苦労だった。人間、取り越し苦労という「心遣い」で、どれだけ心を痛めることか。「目を上げてみると」、直訳すれば「再び見えるようになると」。日の出前の闇がだんだん明るくなって、周囲が良く見えるようになる、ということだと思われるが、同時に、心の目でしっかりもう一度、起こっている事態をありのままによく見よ、という警告である。「目を伏せて、下ばかり見ていると」、つまり本当に見るべきところを見ていないと、「心配」の種ばかりが、大きく膨らんで、それしか見えなくなるよ、と言っているかの如くである。もう「石は既に」転がされていた、そういう信仰の歩みの中での経験、人生での経験を、皆さんはしたことはないか。「その日の苦労は、その日だけで十分である」。
さすがに「やれうれしや」とは思わなかったろうが、おかしく、不審に感じたのは確かだろう。それで女たちが墓の中に入ると、肝心の主の遺体が見当たらない。代わりに白い衣を着た若者がそこに座っていて、(その素性は誰か、また何をしていたのかも、全く不明である)、彼が告げて言うには、「あなたがたは十字架に付けられたナザレのイエスを捜しているが、あの方は復活なさって、ここにはおられない」というのである。
マルコの復活の物語は、これだけである。極めてシンプルなのである。墓を塞ぐ大きく重い石が、転がされていたこと、そして墓が空だったこと、それだけである。復活伝承の最も古い形は、このマルコの伝える物語の素材となった言い伝えだろう、そしてそれは、主イエスの最も身近な場所で仕えていた女弟子たちが伝えたものだろうと、聖書学者たちは推測をする。
初代教会には、復活にまつわる伝承が、いくつもいくつも伝えられていたのだろう。12弟子ばかりでなく、主イエスと親しくふれあった様々な人々が、主イエスの復活の出来事にそれぞれの生活の中で体験したのである。ところが、その多様な復活体験は、一つの共通点を持っているのである。それは、人間の目論見が、見通しが、全く外れていたということ、さらに人間の思いや願いとは、全く違う方向から、神は働かれ、人間の目からしたらまったく不思議と怖れ以外ないような、出来事をもたらされることである。石は転がされ、墓は空なのである。
こういう詩がある。フリードリッヒ・シュバーンエッケ(ドイツの編集者)の作である。「人々は空を見上げて/待っている/あそこから来る人を/でも空からは/来はしない/見上げていても/無駄なのだ/そうしているうちにあの人は/人々の背後から/いらっしゃるのだ」。