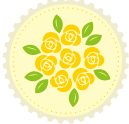
「会議は踊る、されど進まず」。1814年9月に開かれたウィーン会議の様子を風刺した言葉で、フランス全権タレーランの,またはメッテルニヒの秘書の言葉と伝えられる。舞踏会や宴会等、余興が多いわりに,肝心の会議、審議が紛糾難航する有様を皮肉ったものとして知られている。ウィーン会議への参加国は、正統主義を理念に掲げて話し合いを行ったが、領土問題をめぐる利害対立などが絡み、話し合いはなかなか進展しなかった。 そんな中、会議の主催国であるオーストリアは、参加国の親睦を深めて、会議を円滑に進めようと、舞踏会や宴会を何度も開いたのである。それで舞踏会は盛り上がる一方であったが、会議はぜんぜん進まず、この状況を皮肉って、「会議は踊る、されど進まず」 という言葉で風刺されたのだという。
確かに参加者同士の利害が複雑に絡み合うような、国際「会議」というものは、今日もそんな形相を呈するのかもしれない。去る6月、英国南西部コーンウォールで、主要7カ国(G7)首脳会議が行われた。新型コロナウイルスのパンデミックが始まって以来、各国首脳が初めて対面で集まる機会となり、歓迎レセプションにはエリザベス女王も出席した。その際、各国首脳との記念撮影で、女王は場の空気をほぐそうとするかのように、隣のボリス・ジョンソン首相にさりげなく声をかけた。「あなたたちは楽しんでいるように見せなくちゃならないんでしょ、大変ね?」、これにジョンソン首相は、「はい、もちろんです。でもこう見えても、私たちは楽しんでいるんですよ!」と切り返し、首脳陣たちの笑いを誘ったという。国際会議の実際をよく知っている人の、当意即妙、見事なやり取りである。
古代メソポタミアには、一般に「神々の会議」という観念が流布していた。人間たちが町や村の集会場所に集まり、顔を突き合わせて、寄り合いや会議を行い、共同体の運営を行うように、神々も天上で会議を開催し、世の動向を定めるのである、と。この国でも、ある決められた月に(神無月)、神々が特定の場所に集まり、人と人との縁や、運命を定めると人々は考えていたとされる。ただイスラエルは、唯一神教的な宗教思想を持つゆえに、その会議は、神々が自由に論議するような民主的なものではなく、唯一の神ヤーウェの独擅場的な色彩が強かったとされる。会議というよりは、神ヤーウェを裁判長として、審問や証拠の吟味が行われ、審判が下される裁判の場というような雰囲気である。
預言者ゼカリヤは、預言者ハガイの後を享けて活動した捕囚後の預言者である。旧約の預言者の中では最も遅い時代、第二神殿の造営時期にあたり活動した人である。多大な労苦の末、ともかくもエルサレム神殿は再建されるのだが、半世紀以上もバビロンに捕らわれていた同胞たちの信仰の方が、より深刻な問題であった。敗戦後、荒れ果てたエルサレムに帰って、再び生活を立て直さなければならないという課題に、ユダヤの人々は強い危惧を抱き、バビロンを去ることに躊躇する人々も多かったのである。そういう心が委縮した人々の心を奮い立たせ、励ますという務めが、ゼカリヤに課せられたのである。
ゼカリヤ書は、1章から8章までは、「幻」という黙示文学的ではあるが、預言者自身に遡る託宣が記されているが、9章以下は、時代は下って、マカベア時代に語られた託宣が
記されたと考えられている。今日の個所では、裁判長たる神ヤーウェのみ前に、大祭司ヨシュアが立たされて、その責任が問われる、という極めて顕著に法廷の場面が描かれている。検事役は「サタン」であり、弁舌鋭く、かの聖職者を告訴するのである。サタンが検事役というのは、ヨブ記1章にもみられる舞台設定である。「サタン」という名前も、元々は「告発する者」から来ており、旧約時代のサタンのイメージを、テキストはよく伝えていると言えるだろう。そもそもサタンは、人間を悪の道に誘惑する、悪の存在という、後の時代の観念とは異なり、神のみ前に仕える御使いのひとりで、人間の隠れた罪を告発するという役割を担った存在なのである。だから「検事」という役柄は、サタンにとって最も似つかわしい姿かもしれない。そしてこの検事役サタンに対抗して、被告を弁護する御使いも登場することが興味深い。「法廷」という場、「検事」あるいは「弁護士」という職業が、紀元前のペルシャ時代に、すでに存在し、機能していたことが想定されるので、法曹の世界とは、長い歴史に培われていることに目が開かれる。それだけ人間は争い合いながら歴史を歩んで来たのであり、またその調停も必要不可欠だったということである。
さて、被告人たる「大祭司ヨシュア」であるが、実際どのような人物か、どのような働きをした人か定かではない。モーセの後継者ヨシュアを象徴的に示唆しているのかもしれない。彼は「汚れた衣を着ており」、弁護人たる御使いから「燃えさし」、つまり「燃え残り、消し炭」、と評されている。甚だ見栄えのしない、疲弊した姿であり、大祭司としての威厳の象徴としての被り物(ターバン)も被っていない有様である。
この表象はまさに長年、異教の地、偶像の町バビロンで暮らさざるを得なかったユダヤの人々の姿と、二重写しに語られていると思われる。エルサレムがバビロニアによって壊滅させられ、祖国が崩壊し、荒廃するままに放置された、かつての美しい都と、そこに暮らしていた人々の今の有様である。そのようなつらい憂き目をみたユダの人々を、再び祖国に立ち戻らせるという課題の前に、ゼカリヤは置かれているのである。
ここでの「幻」は、みじめな風体をした大祭司が、再び晴れ着に装われ、頭には威厳のしるしであるターバンを巻かれ、美しい姿に変えられるというものである。これは神殿が再建され、またそこで祭儀が行われ、そこで信仰者が再び主に祈り、賛美するという光景を、人々に想起させる意図があるだろう。しかし、神殿が再建されても、そこで荘厳な祭儀が再開されても、それが表面的なことに終始していたら、真に祖国の再建は全く覚束ない。即ち、「神ヤーウェが共におられる」という確信こそが、再建の力となるのである。
この章の最後に、「七つの目がある一つの石」について語られている。この石は、再建される神殿の礎となる隅の頭石を意味しているであろう。再建される祖国の礎に、7つの主の瞳、完全なる神の眼差しが据えられている。遥か天空の見えない所にではなく、自分たちの歩む一歩一歩を神が見守っておられ、目を注いでくださっている。インマヌエル、神共にいますことが、私たちにとっても、一番の安心、安全に他ならないのである。