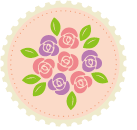
皆さんに「おふくろの味」といえる食べ物があるだろうか。決して高価ではないが、美味しく、懐かしい郷愁の味である。私の世代ならば、「煮物や煮付、漬物、味噌汁」の類だろう。以前、あるアメリカ人と「おふくろの味」について話した時に、彼は「ステーキかな?」と答えてくれた。今の子ども達も、「おふくろの味」が皆無ということはないだろう。昔とメニューは違っても、必ずどこかに「懐かしい味」というものは、記憶の中に刻印されているのではないか。
「滋味」という言葉がある。ある辞書ではこんな風に説明されている。「滋味とは、奥深いうまみを表現する言葉で、『滋味豊かな料理』などと使う。『滋』はうるおう、増やす、(草木が)茂るなどを意味し、草木をうるおす恵みの雨『慈雨』、身体をうるおす栄養が豊富な『滋養』といった熟語を形成する。『滋味』も本来は『栄養豊富でおいしい味』のことを言った。しかし、栄養豊富なものは必ずしもうまいものとは限らず、また、糖分や脂分や塩分をたっぷり使った体に悪そうなものがとびきりうまかったりするのが現実なので、『滋味』も、誰にでもわかる幼稚なうまさの表現には用いられず、驚くほどうまくはないが、食べるうちに栄養が体をうるおすような感じがして、がまんして食べ慣れれば必ずしもまずいというわけではない」(笑える国語辞典「滋味」の項より)。
「滋味」とはただ美味しいだけではない。身体をうるおし、養うが、時にはあまりおいしくない、ということもあり、食べ慣れると、その味わいの良さが分かる、というのである。一筋ならない味のこと、「おふくろの味」とはそういういものかもしれない。
今日の聖書個所には、主イエスが「食べ物」に喩えられ、信仰者はその「まじりけのない霊の乳」に養われるべきだと、勧められている。「霊の乳」なるものが、どんな味なのかは、実際知る由もないが、赤ん坊が、乳なしには成長できないように、信仰者には、魂の食べ物が必要であることに、異論はないであろう。たとえ神への信仰がなくても、人間には、肉の糧ばかりでなく、魂を養う糧、滋養が必要なのである。ここでそれを「乳」と表現していることに興味を覚える。最初からしっかりと硬いものを食べさせ、大人が美味しいと感じる食べ物を子どもに食べさせるのは、虐待であるだろう。信仰の養いや成長のためには「乳」が必要だと、この手紙の著者は知っているのである。神は、そんな大人の食べ物ばかりを食べることを強いることはしない。また贅沢な三星レストランの佳肴珍味を、殊更に勧めるグルメでもない。赤ん坊にとって、「乳」という生きるになくてならぬものを与えられる神は、私たちに対しても同様、なくてならぬものをもって養われるのである。
さて、3節「あなたがたは、主が恵み深い方だということを味わいました」というみ言葉がある。この「恵み深い」という言葉の意味は広く、たとえば食べ物について用いられると、「おいしい」という意味になる。「あの時のごはんはおいしかった」と、頭ではなく身体で覚えている味覚のことである。昔、教会学校のキャンプで、皆で飯盒でご飯を炊き、あり合わせの材料でおかずを作り、皆で丸くなってごはんを食べた時の思い出がよみがえってくるようだ。「あなたがたは、主のおいしさを味わいました」。そう訳してもよいかもしれない。旧約聖書の詩編の詩人もこう歌っている。「味わい、見よ、主の恵み深さを」。つまりみ言葉は、わたしのこころと身体と魂の全霊をもって〈味わう〉ものなのだ」、 そのようにして、神の恵みの味わいを忘れることができない私たちは、何と幸いなことだろう」(詩34編9節)
「主のおいしさを味わったわたしたち」という言葉は、実にリアルに心に響く。教会に
集う人々は、皆、この体験をしていると思う。教会で食べるご飯は、決して贅沢なものではない。教会では、皆に「うどん」が供されることが多い。手っ取り速く当たり前の地味なメニューである。全国、津々浦々で味わいや「かやく」の違いはあっても、どこの教会のうどんもそれぞれの味わいに富んでいて、とてもおいしい。
そのおいしさの原点はどこにあるか。それは調理してくれる「マルタ」の働き抜きには、生まれないものであろう。しかし、そのおいしさは、「主が共におられる」こと故なのである。主がかつて、人々と共に喜びの内に、同じ椀から飲み食いされた、その思い出が、「おいしさ」の原点であるだろう。今も私たちは、その思い出を新しく心に刻み、次の世代へとバトンタッチして行くのである。その輪の中に、主は共におられるのである。
現在、「新型コロナ感染症」の影響を考慮して、教会に皆で集まり、食事を共にすることを、「自粛」としている。これが残念な一番の理由は、「主のおいしさ」を共に味わう、この単純で、当たり前のことができないからなのである。再び同じひとつの食卓を囲める日が、一日も早く来るように祈りたい。
今日の聖書個所の後半には、「捨てられた隅のかしら石」の譬えが語られる。福音書にも同様に記述されている。十字架につけられた主イエスを、実に「捨てられた石」として理解することが、初代教会の「キリスト論」であったことが伺える。人々が、建築家が、不要で役に立たないとして「捨てた石」が、建物の土台を支える「親石」になった、というのである。この譬えもまた、「主のおいしさ」から理解することができるのではないか。
大阪では「始末」の大切さがよく語られる。そこでの精神は、この一語に費やされている。『商家の家訓』(徳間書店、吉田豊氏編訳)の中でも、「始末とは、『始』と『末』、すなわち、始めと終わりのことで、『経済活動における一貫した計画性』というのが本来の意味だった」と語られている。料理もまた「始末」であり、食材すべてを無駄にせず、捨てることなく使い切るところにある。例えば「ほるもん」という言葉も、元々は「放る物」、つまり「捨てるもの」から来ていると言われる。ところがその「放るもの、捨てるもの」を料理すると、格段においしい。一度食べれば「病みつき」になる。それが「始末」ということである。物を無駄にしないというばかりでなく、捨てられ、顧みられないものの中にある真実を探り、見出し、最善に用いて、この上ないものとする、のである。
神のなさることは「始末」である。人間の目には不思議に見えるが、「一貫した計画性」をもって、救いの出来事を起こされるのである。その見事さは「主のおいしさ」の中で開示されている。